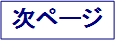
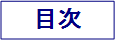
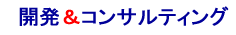
まず、ムダな業務とは何かを理解する必要があります。ムダな業務とは付加価値を生まない業務、又は付加価値が非常に低い業務です。分かりやすく言えば、売上や利益を全く増やさない業務、又はほとんど増やさない業務です。よって、通常、次の5種類が考えられます。
などです。
業務に対する人の意識(考え方や価値観)を変えなければ、ムダな業務を発見することはできません。なぜなら、業務は人の考え方や価値観に基づいて行われるからです。逆に、人の考え方や価値観が変われば、ムダな業務を発見することは容易にできるのです。
目の前にムダな業務があっても分からないのは、そもそも、ムダな業務を発見しようとしていないからであり、業務を改善・効率化しようとしていないからです。
人の考え方や価値観を変えなければ改善・効率化ができないのは、工場現場の作業の改善・効率化でも同じです。つまり、現場作業の改善(KAIZEN)を行うには、まず、人の考え方や価値観を変える必要があるのです。 このために、工場現場ではいろいろな考え方や技術が活用されているのです。
よって、これから解説する考え方と読者(あなた)の考え方を比較してみてください。それはおかしいとか、そんな馬鹿なと思ったとき、あなたの考え方の方がむしろおかしいのであり、そのような人が多い会社にはムダな業務が多いのです。
なぜなら、これから解説する考え方は、世界中の多くの工場で100年以上用いられているIE(管理工学)の考え方や50年以上用いられているVE(価値工学)の考え方だからです。
今回は、IEの考え方を説明し、次回IEを用いてムダな業務を廃止・削減する方法を説明します。そして、次々回、VEの考え方を説明いたします。IEは世界中の工場現場の改善に用いられているので、工場管理者にとっては常識です。しかし、IEを業務(デスクワーク)に適用している企業はあまりないと思いますので、多くのホワイトカラーにとっては初めて出会う考え方だと思います。
価値のないムダな業務を廃止・削減するには、ムダな業務を浮き彫りにしなければなりません。そのための1つの方法は、工場の作業改善に用いるIE(管理工学)の考え方と技術を業務に適用することです。なぜなら、IEの目的は付加価値を高めることであり、IEは価値のないムダな作業を廃止・削減したり、価値の低い作業を価値の高い作業に変えたりする技術だからです。
したがって、工場現場の作業にIEを適用するときには、何はともあれ、最初に工程分析を行います。工程分析にはいろいろな分析がありますが、その中で最も重要な分析は、各工程(作業)が価値を生んでいるかを明確にする分析です。これを価値分析と言います。なお、工程分析はJIS規格になっていますので、興味のある人はJIS規格を見てください。
価値分析について説明する前に、IEの長所と短所を簡単に説明しておきます。IEの長所は、材料や部品などの物の動きや手足の動きなど、目に見える作業の分析・改善に適していることです。IEの短所は、人の考え方や価値観など、人の頭の中は分析できないので、思考・判断を要する業務(デスクワーク)の改善・効率化には適していないことです。
ただし、価値分析だけは例外なのです。価値分析の対象を作業から業務に変えることによって、価値を生んでいる業務と生んでいない業務を明確に区別することが出来るのです。よって、業務の改善・効率化ができるのです。、
一方、VE(価値工学)の長所と短所はIEとは逆です。つまり、VEの長所は人の考え方や価値観など、人の頭の中を分析することができるので、思考・判断を要する業務の改善・効率化に適していることです。VEの短所は目に見える物や手足の動きなどの分析ができないので、作業の改善には適していないことです。
なお、IE、及びVEについて詳しく知りたい方は、コスト削減・原価低減の考え方と技術をご覧ください。あるいは、『文科系のためのコスト削減・原価低減の考え方と技術』(守屋孝敏著 電子書籍 アマゾン及び楽天で販売)をご覧ください。文科系のために分かりやすく解説してあります。
さて、工場で価値分析を行うためには、まず、各工程を、加工・組立、運搬、検査、停滞(在庫)の大きく4つに分類します。そして、実際の工程(作業)を調査分析してどの分類に属する工程(作業)かを明確にするのです。これが価値分析です。
なぜなら、加工・組立の工程は価値を生んでいるが、運搬、検査、停滞(在庫)の各工程は価値を生んでいないからです。よって、工場では運搬、検査、停滞(在庫)の各工程をできるだけ廃止・削減するのです。
当然でしょう。材料や部品や製品をいくら運搬しても、検査しても、あるいは在庫しても売上や利益は増えません。それどころか、いずれも時間(コスト)がかかるので、利益が減ってしまい、付加価値が減ってしまうのです。つまり、これらの工程(作業)は無価値なのです。
ところで、この考え方を始めて知った読者の皆さんは、それはおかしいとか、そんな馬鹿な、などと言っていませんか。工場なら運搬も検査も在庫も必要だろうなどと言っていませんか。
例えば、トヨタ生産方式(ジャスト・イン・タイム)は在庫(停滞)をできるだけゼロにするために考え出された生産方式なのです。また、ベルトコンベアシステムは運搬時間をできるだけ削減するために考え出された方法なのです。さらに、材料や部品、製品などを検査する際に、全数を検査しないでランダムに抜き取って検査する抜き取り検査がありますが、これは統計学を用いて効率的に検査する方法です。
このように、工場現場では在庫の廃止・削減だけでなく、運搬や検査の廃止・削減を行って、これらにかかる時間(コスト)をできるだけ廃止・削減し、付加価値の減少を防いでいるのです。
この価値分析の考え方と技術を業務(デスクワーク)に適用することによって業務の価値分析を行うことができます。ただし、そのためには、業務の特徴を踏まえて、価値分析の対象を業務に変える必要があるのです。と言っても難しくはありません。すなわち、
そこで、何をしているのかを明確にしてから価値分析を行う必要があります。つまり、予め、業務(デスクワーク)を分類してから価値分析を行います。この点は、工場現場の作業(工程)の価値分析でも同じです。工場現場では、予め、各作業(工程)を、加工・組立、運搬、検査、停滞(在庫)の4つに分類しました。
以上の考え方の基で、価値分析の対象とする業務を次のように分類します。
(1)作業や業務を計画・立案・設計する業務 (2)書類や業務ファイルなどを加工・編集・処理する業務(工場における加工・組立に相当) (3)書類や業務ファイルなどをチェック・照合・確認する業務(工場における検査に相当) (4)書類や業務ファイルなどの内容を報告・連絡・通知する業務(工場における運搬に相当) (5)書類や業務ファイルなどを保存・保管・在庫する業務(工場における在庫に相当) (6)会議・打ち合わせ・相談する業務は、その目的が意思決定(計画・立案・設計)であれば(1)に、情報の伝達(報告・連絡・通知)であれば(4)に分類します。よって、すべての業務(デスクワーク)を、(1)計画・立案・設計、(2)加工・編集・処理、(3)チェック・照合・確認、(4)報告・連絡・通知、(5)保存・保管・在庫の5つに分類できます。
なお、情報の収集業務はどの業務にも付随する業務です。つまり、収集した情報を基に計画・立案・設計したり、収集した情報をチェック・照合・確認したり、収集した情報を報告・連絡・通知したり、収集した情報を保存・保管・在庫したりします。
さて、上記(1)及び(2)の業務については、価値を生んでいるかいないかは詳細に分析してみないと分かりませんので、次々回以降、VEを用いて分析します。しかし、上記(3)(4)(5)の業務は明らかに価値を生んでいないムダな業務ですので、次回、これらのムダな業務を廃止・削減する考え方・方法について説明します。
と書くと、多くのホワイトカラーは、「何をバカなことを言っているのか、部下の仕事をチェックするのは上司の重要な仕事だ、部下を教育することが上司の役割だ」とか、「関係者に報告・連絡しなければ仕事が回らないではないか」とか、「ファイルを保存しておくのがなぜムダとなるのか」などと言います。
実は、このような意識(考え方・価値観)こそが間違っており、ムダを生み出しているのです。よって、「ホワイトカラーの意識を変えなければ業務の改善・効率化ができない」ことがよく分かると思います。
ここで、読者の皆さんの意識を変えるために、再度、確認します。どんなに時間(コスト)をかけて書類や業務ファイルをチェック・照合・確認しても、書類や業務ファイルの内容を報告・連絡・通知しても、あるいは書類や業務ファイルを保存・保管・在庫しても売上や利益は増えません。増えるのはコストだけです。ですから、これらの業務を行えばいずれも付加価値が減ってしまうのです。つまり、これらの業務は無価値であり、できるだけ廃止・削減する必要があるのです。
ちなみに、業務分掌規程にある大分類業務、中分類業務、小分類業務などの名称が「◯◯のチェック・照合・確認」「◯◯の報告・連絡・通知」「◯◯の保存・保管・在庫」などとなっていれば、その業務分類に属する業務すべてがムダな業務ということになります。
業務の価値分析を行うには、分類した5つの業務を色分けするか、工程記号(JIS記号)を用いて、業務の流れ(業務フロー、ワークフロー)に沿って記号を書いて行きます。記号は自由に作成してもかまいませんが、JIS記号を用いれば分かりやすいです。
ちなみに、筆者が使っている業務の工程記号は、JIS記号を基に作成したもので、計画・立案・設計(◎)、加工・編集・処理(◯)、報告・連絡・通知(⇒)、チェック・照合・確認(◇)、保存・保管・在庫(▽)です。
既に、「3-5 職務内容の明確化」で職務の見える化(職務記述書の作成)を行っておりますので、職務の流れに沿って工程記号を書いて行きます。職務記述書の工程記号記入欄に記入するだけです。
多くのホワイトカラーは工程(価値)分析を行ったことがないでしょうが、以上のように、工程(価値)分析は分かりやすく、しかも簡単にできるのです。
次に、各職務の時間を計画設定します。設定方法は、「3-4 業務分類ごとの業務時間の計画設定と測定記録」で既に説明いたしました。この時には業務分類ごとの時間しか計画設定しなかったので、ここで各職務の時間を計画設定します。
各職務の時間を計画設定すると言うことは、個々の職務の予定時間(コスト)を明確にすることですから重要です。なぜなら、価値を生んでいる職務のコストと価値を生んでいないムダな職務のコストが明確になるからです。ただし、この時間はあくまで計画(予定)時間です。実際の時間(コスト)は職務が終わってからでないと分かりません。
ここで、さらに重要なことを書きます。各職務の時間を計画設定する際に、計画・立案・設計(◎)、加工・編集・処理(◯)、チェック・照合・確認(◇)などの時間は容易に計画設定できますが、報告・連絡・通知(⇒)、保存・保管・在庫(▽)などの時間を計画設定するには注意が必要です。
なぜなら、これらの時間は、パソコンを用いてこれらの業務を行う場合はクリックする瞬間の時間に過ぎないと多くのホワイトカラーは考えるからです。このため、これらのムダな時間を明確にできません。
しかし、報告・連絡・通知をするには報告書・連絡書・通知書などを書いて、修正・確認したり、報告・連絡・通知をする人や部署を確認したりします。そこで、何人に対して、あるいは何か所に対して報告・連絡・通知をするのかを業務要件として職務記述書に記入しておく必要があります。また、保存・保管・在庫をする場合は、何時間、あるいは何日間、保存・保管・在庫しておく予定(計画)なのかを職務記述書に記入しておきます。
実は、工場における工程(価値)分析は対象が材料や部品などの物であるため、物の動きを追っかけて分析を行います。したがって、物が運搬されればその運搬時間を、物が停滞(在庫)していれば、その停滞(在庫)している時間を測定したり、作業者に聞いて概略設定したりします。
しかし、多くの企業では、書類や業務ファイルが停滞(保存・保管・在庫)していても、その時間を測定したり概略設定したりしません。なぜなら、多くの企業では業務(職務)の納期(スケジュール)管理を行っていないため、業務(職務)の停滞(保存・保管・在庫)を問題だと捉えていないからです。さらに言えば、業務(職務)の停滞時間は人件費がかからないのでコストにはならないと考えているのです。このために多くの損失を生んでいるのです。
Ⓒ 開発&コンサルティング