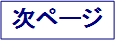
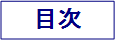
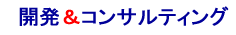
各自で職務記述書の各職務に工程記号を記入し、各職務の時間を計画設定しましたら、少なくても1ヵ月間について、工程記号ごとに業務(職務)時間を集計し、円グラフを作成します。すると、通常は、全業務(職務)時間のうち、停滞(保存・保管・在庫)時間が最も多いので、停滞から廃止・削減の検討を行います。ちなみに、停滞時間はもちろん、業務時間に含まれます。なぜなら、業務が停滞すれば、それだけ業務コストが掛かるからです。
業務(職務)の停滞(保存・保管・在庫)は価値を全く生まない無価値業務(職務)であり、しかも、通常、最も時間が長く、ムダなコストが多くかかっているのですから、最初に廃止・削減の検討を行うのです。
実際、筆者が数十社の一部上場企業で調査したところ、全ての業務時間の60%~80%の時間が停滞(保存・保管・在庫)となっていました。つまり、多くの書類やファイルを保存・保管・在庫したまま、何日間も何週間も利用されずに放置されているのです。御社でも調査してみて下さい。ただし、法令で保管が義務付けられている書類やファイル、及び必要の都度、何度も利用するマスターファイルなどは除きます。
時間(コスト)をかけて加工・編集・処理した書類やファイルを保存・保管・在庫しておけば、それだけでコストがかかるので、損失を生みます。つまり、付加価値が減るのです。まして、何日間も利用せずに放置していれば大きな損失となります。
たとえ職務をIT化して処理時間を短縮しても、その職務を何時間も何日間も停滞させたのでは何もなりません。要するに職務の納期(スケジュール)短縮を図らなければならないのです。また、職務が停滞すれば意思決定と実行がそれだけ遅れるわけですから、顧客やユーザーを待たせるだけでなく、他社に遅れをとることにもなります。よって、その原因を追求して停滞時間をできるだけ削減しなければなりません。
書類やファイルを1日(8時間)保存しておくと、どのくらいコストがかかるか計算したことがありますか。おそらくないと思います。そのため、その損失金額が分からないのです。大量の書類やファイルを何日間も保存・保管・在庫しておけば、非常に大きな損失となります。書類やファイルの保存・保管・在庫は会社の財産を利用しないで放置しておくことになるからです。
工場では、「在庫は諸悪の根源である」という言葉があります。工場管理者ならば誰もが知っている言葉です。しかし、実は、未だにそうは考えない中小メーカーもあります。むしろ、材料や部品の在庫が十分にあった方が、在庫切れがなく、手待ちもなくなるので都合が良い、と考えるのです。
しかし、ご存知のように、トヨタ自動車では在庫を少しでも削減するために、トヨタ生産方式を生み出したのです。在庫をゼロに近づけるために、必要なものを、必要な時に、必要なだけ作るのがジャスト・イン・タイム方式です。この考え方はトヨタでは業務においても全く同じです。
トヨタでは、在庫がいかに悪いかを説明するために、「日本人は農耕民族だからいけないのだ、狩猟民族にならなくてはいけない」と言っています。つまり、生きるために必要な分だけ保存・保管しておけば良いということです。農耕民族である日本人は何でも貯める癖があります。特に財産は貯めるのです。しかし、トヨタでは財産は貯めるものではなく、利用するもの、活用するものだと考えます。
実は、材料や部品の在庫は問題だが、書類やファイルの在庫は問題ではないと考える企業が多いです。それは、書類やファイルの在庫金額(コスト)を計算したことがないからです。金額(コスト)に換算すれば、いかに書類やファイルの在庫が大きな損失かが分かります。
ちなみに、筆者が業務の改善・効率化のコンサルティングを行った企業では、書類やファイルの在庫金額を計算する際に、最初は業務時間を基に計算します。つまり、業務の在庫金額を1日8時間として計算します。しかし、実際の在庫金額は業務時間(コスト)だけではありません。
なぜなら、業務を行っていない夜中でも在庫しており、夜中でもハードディスクや倉庫(ストレージ)費用、保管管理費用などがかかっているからです。よって、本来、実際の在庫金額(コスト)は1日を24時間として計算しなければ正確な在庫金額(コスト)は算出できません。
さて、これまで説明したことを改めて箇条書きでまとめておきます。材料や部品と同様に、書類やファイルは企業にとっては財産です。なぜなら、時間(コスト)をかけて必要な情報を収集し、それを基に時間(コスト)をかけて加工・編集・処理したものだからです。この財産を保存・保管・在庫しておくと言うことは、
よって、書類やファイルを保存・保管・在庫しておくことは、大きなコストがかかり、損失となりますから、できるだけ保存・保管・在庫しないようにします。
なお、業務要件として、一定期間、保存・保管・在庫しておかなければならない、契約書、決算書、取引先情報、顧客情報などは除きますが、それ以外は、できるだけ停滞(在庫)時間を削減します。
書類やファイルの保存・保管・在庫をできるだけ廃止・削減するためには、何はともあれ、納期(スケジュール)管理をしっかりと行うことです。業務(職務)のジャスト・イン・タイムを実施できれば理想的ですが、少なくとも納期管理を行い、そのうえで少しでも管理レベルを上げる必要があります。
工場の現場作業の納期(工程)管理を行っている工場管理部門の人たちが、自分が行っている業務の納期管理を行わないのは、「医者の不養生」「紺屋の白袴」ということです。
なお、書類・ファイルの保存・保管・在庫の廃止・削減だけでなく、ムダな書類・ファイルそのものの削減については、「4-9 ムダな書類・ファイルとムダな会議の廃止・削減」に、具体的な方法が書いてあります。また、トヨタの書類削減事例も書いてありますので、参考にしてください。
次に廃止・削減の検討をするのは、業務(職務)内容の報告・連絡・通知の業務(職務)です。これも価値を全く生まない無価値業務(職務)ですので、ムダですから、できるだけ廃止・削減をします。
ところが、多くの企業ではコミュニケーションが重要とされていることから、いわゆる、報・連・相(報告・連絡・相談)は重要であると考えており、これらの業務(職務)は価値を生んでいると勘違いしているのです。
いろいろな情報を、多くの人に報告・連絡・通知をするのは、実は集団主義の現れです。みんなで決めて、みんなで実行するために報告・連絡・通知をするのです。仮に、1人で決めて、1人で実行するのであれば、報告・連絡・通知は全く必要ありません。また、そのための会議・打ち合わせ・相談も必要ありません。
日本では、いわゆる報・連・相(報告・連絡・相談)が重要だと考えていますが、外国人から見ればおかしな風習に見えるのです。なぜなら、仕事を指示された人だけが仕事を行い、その結果を指示した人に報告すれば良いからです。そして、その内容を関係者にだけ報告・連絡・通知すれば良いからです。
日本ではその業務(職務)に関係のない人たちにまで報告・連絡・通知するのです。その必要があるのでしょうか。しかも、その業務(職務)に関係のない人までが、「俺は聞いてない」などと言うのです。自分には関係のない業務(職務)であるにもかかわらず、何でも知っておきたい、何でも見ておきたい、とみんなが思うのが集団主義なのです。
集団主義がなぜいけないのかは、本稿の最初に書きました。もう1度よく読んで下さい。報告・連絡・通知は、「みんなで決めて、みんなで実行する」ために必要な業務(職務)であり、集団主義の最も典型的な業務(職務)なのです。したがって、できるだけ権限を委譲し、1人で決めて、1人で実行するようにすれば、報告・連絡・通知はほとんど必要ないのです。
そもそも、多くの企業では、意思決定と実行に必要のない情報まで報告・連絡・通知させる場合が多いです。つまり、単に、「知っておきたい」「見ておきたい」だけの情報まで報告・連絡・通知させているのです。このために、コストがいくらかかっているか調べたことがありますか。どの企業でも報・連・相を重視しているので、膨大なコスト(損失)になっているのです。御社でもコストを計算してみて下さい。各自の職務記述書の報告・連絡・通知の職務時間を合計して賃率をかければコストが計算できます。
意思決定をする人やそれを実行する人だけに、つまり、関係者だけに必要な情報を伝達(報告・連絡・通知)すれば良いのです。当たりでしょう。ところが、集団主義に基づく日本の企業では、コミュニケーション(報・連・相)を重視しているために、関係のない人にまで情報の伝達(報告・連絡・通知)をするのです。したがって、大きなムダ(損失)になっているのです。個人主義に基づく欧米の企業から見ると、日本の企業の報・連・相はおかしな風習なのです。
業務(職務)内容のチェック・照合・確認がムダであることを説明する前に、工場の検査の実態はどうなのかを説明しておきます。実は、多くの工場でも未だに検査は絶対に必要だ、ムダではないと考える人が大勢いるからです。
特に中小メーカーでは、「もし、加工途中で不良品が作られてしまったら、不良品がそのまま最終工程まで加工・組立されることになるので、大きな損失になってしまう」と考えます。そのため、加工途中で何度も中間検査を行うのです。
確かに、その通りですが、例えば、トヨタ自動車の工場内に中間検査工程はありません。トヨタでは、「次工程はお客様」と言って、次工程には絶対に不良品を渡してはならないとしています。つまり、各工程で絶対に不良品を作らないようにしているのです。
また、トヨタでは協力工場から搬入される材料や部品の受入検査も行っていません。協力工場に対して、不良品を絶対にトヨタの工場に入れてはならないことを約束(契約)しているからです。これを品質保証契約と言います。
ただし、トヨタでは製品の出荷検査だけは行っています。万一、不良品を出荷し、販売してしまったらお客様に大変な迷惑をかけることになるからです。また、もし、リコール(呼び戻し)となれば、販売した製品や部品を回収し、交換したり損害賠償したりしなければならないからです。したがって、協力工場でも同様に、材料や部品の出荷検査だけは行っているのです。
よって、業務(デスクワーク)においても、トヨタでは部下の仕事をチェックしていません。よって、御社でも部下の仕事をいちいちチェックするのは止めて、部下の仕事は部下に任せてください。そのためには、業務ミスを絶対にしないように、責任を持って業務を行うように、部下をしっかりと教育しなければいけません。ただし、顧客や取引先に提出する書類やファイルの最終チェック(出荷検査と同じ)だけは行って下さい。
実は、上司が部下の仕事をいちいちチェックしている企業では、頻繁に業務ミスが発生しているのです。なぜなら、「どうせ上司がチェックするのだから、多少いいかげんでも構わない」「上司が喜んでチェックしているのだからチェックさせてあげれば良いではないか」などと部下が考えているからです。これはアンケートを取ってみれば分かります。
多くの担当者が、「業務は80%完成すれば良い」と考えている企業では、管理者が100%完成させているのです。そのような企業で、従業員の性格を調べてみると、管理者は完全主義・完璧主義の人が多く、担当者は80%主義とも言える、いいかげん(大雑把)な性格の人が多いです。
また、上司が部下の仕事をチェックするのは、これまでに培った知識・経験でできるので、上司にとっては楽にできる仕事です。しかも、上司は部下に対して優越感を味わうことができる嬉しい仕事なのです。
よって、多くの管理者は、このように楽にできる業務を優先して行うのです。そして、売上や利益を増やすための難しい業務は後回しにするのす。つまり、後ろ向き(守り)の業務を優先して行い、前向き(攻め)の業務は後回しにするのです。
多くの企業で実際に調べてみると、後ろ向き(守り)の業務の割合が前向き(攻め)の業務の割合よりもはるかに多くなっています。通常、守りの業務は業務量全体の80%以上となっています。実際に、96%になっていた一部上場企業もありました。これがいわゆる大企業病の正体なのです。しかし、実は中小企業でも同じ傾向でした。これでは、企業は成長・発展しません。
「部下の仕事をチェックするのは管理者の重要な仕事だ、部下を育てることが管理者の役割だ」などと言っている管理者は反省してください。部下と一緒に、売上や利益を増やすのが本来の仕事です。
部下の仕事をチェックするなどの内部管理業務はできるだけ廃止・削減して、管理者の業務ベクトル(方向)を内部から外部(市場)に向けるようにしなければなりません。これについては、「4-7 市場(顧客)志向による内部管理業務の廃止・削減」で詳しく説明いたします。
以上、書類やファイルの保存・保管・在庫、報告・連絡・通知、チェック・照合・確認など、明らにムダな業務の廃止・削減について説明いたしました。
一見、価値があると思われる、計画・立案・設計、及び加工・編集・処理の業務については、VEの考え方を適用して価値があるか無いかを調査分析します。そこで、次回以降、順次、これらの業務についていろいろな視点で詳細に調査分析して価値があるか無いかの確認を行い、価値がない業務については廃止・削減の検討を行います。
Ⓒ 開発&コンサルティング