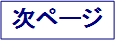
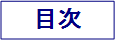
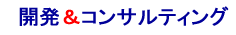
目的思考とは業務目的を経営目的に一致させることであり、すべての業務の目的は経営目的に結びついていなければならないということです。なぜなら、すべての業務は経営目的を果たすために計画・立案・設計され、実施されるはずだからです。
経営目的とは会社経営の目的です。では、会社経営の目的とは何でしょうか。ちなみに、定款に書かれている「目的」は会社経営の目的ではありません。定款には事業内容が書かれている場合が多いです。
会社経営の目的は会社設立の趣旨とか経営理念などに表示されている場合が多いです。しかし、多くの企業では明確になっていない場合が多く、改めて、我が社の経営目的は、「〇〇を〇〇することである」と端的に表現しておく必要があります。
なぜなら、利害関係者に理解してもらい、経営目的を果たすために協力してもらう必要があるからです。なお、経営理念の見直しについては、「5-3 経営理念の見直し」で詳しく説明いたします。
ここで、参考になると思うので、本来、会社経営の目的は何かを説明しておきます。経済学、及び経営学においては、会社経営の目的は「利潤の追求」あるいは「利潤の最大化」であり、経済学者や経営学者が書いた会社経営に関するすべての本や論文はこの目的のために書かれています。
しかし、その一方で、日本人が大好きなピーター・ドラッカーだけは会社経営の目的は、利潤の追求ではなく、「顧客の創造」であると論文に書きました。著書である『現代の経営』にも同じことを書いています。このため、ドラッカーは世界中の学者や研究者、あるいは企業経営者から注目され、急速に名が売れて、次の論文の発表を期待されました。
しかし、ドラッカーはその後、これと言った論文を書いていません。良い論文をたくさん書くのが経営学者の仕事ですから、ドラッカーは自分を宣伝するためにアドバルーンを上げただけだと言われています。このため、経営学者としてはあまり認められておらず、大学の経営学部でドラッカーが授業で取り上げられることはほとんどありません。
ドラッカーは元GM社(ジェネラルモーターズ社)専属の新聞記者であったため、その経験を活かして経営学者になったのです。GM社の社長であったアルフレッド・スローン・ジュニアの経営手腕の基で、GM社が世界一になる過程をドラッカーはつぶさに見ていたのです。そこで、この経験を基に企業経営に関する良い本をたくさん書いています。しかも、元新聞記者であったために分かりやすい文章で本を書くので多くの人に読まれているのです。
さて、会社経営の目的が「利潤の追求」か「顧客の創造」かの議論は、鶏が先か卵が先かの議論と同じだと思います。あるいは、本音か建前かの議論です。つまり、あまり意味のない議論です。いつも本音で話す欧米人はドラッカーが嫌いですが、めったに本音を言わない日本人はドラッカーが大好きなのです。つまり、ドラッカーの心情が日本人の心情に合っているのです。
例えば、日本の経営者は、「お客様に喜んでもらうために会社を経営している」と言います。つまり、会社経営の目的は「顧客の創造」です。しかし、これは建前であって、本音は、「儲けるため」、つまり「利潤の追求」です。なぜなら、儲けなくては会社は倒産してしまうし、会社を大きくできないからです。
さて、ここでは、我が社の経営目的は何かを明確にすることです。各社で改めて良く考えてください。我が社の経営目的が明確になりましたら、次に、その目的を果たすための基本的な機能(役割)は何かを考えてください。それは通常、事業コンセプト(概要)に相当します。つまり、経営目的を果たすためにどのような事業を行うのかです。
事業コンセプトとは戦略ドメイン(事業領域)や事業のビジネスモデル(儲ける仕組み)を表したものです。しかし、これも多くの企業では明確になっていない場合が多いです。そこで、改めて、「◯◯市場をターゲットにし、◯◯という顧客ニーズに応えるために、独自技術◯◯を活用して、◯◯する」などと端的に表現すると分かりやすくなります。
以上のように、会社経営の目的と基本機能は、多くの企業では、通常、経営理念、事業領域、あるいはビジネスモデルなどに具体化されています。経営理念は会社の大黒柱とも言うべきものなので、経営環境が変化しても、通常、変更しませんが、事業領域やビジネスモデルは経営環境が変化すれば変更します。なぜなら、経営戦略を変える必要があるからです
例えば、経営環境が変われば衰退する事業から撤退したり、今後発展するであろう事業に経営資源を集中させたり、つまり事業の選択と集中を行ったり、新規事業開発を行ったりします。つまり、事業の再構築(事業の立て直し、すなわちリストラ)を行って事業領域を変更します。要するに、経営環境が変われば経営戦略によって事業領域を変更するのです。なお、事業領域をなぜ戦略ドメインと言うかといいますと、事業領域は経営戦略に基づいて「戦略的に決めた事業の生存領域」だからです。ドメインは領域という意味です。
ちなみに、動植物にも生存領域があります。例えば、地球の温暖化によって、動植物の生存領域が変化していることはTVでも報じています。したがって、企業も経営環境が変化すれば事業領域を変える必要があるのです。
さて、経営環境は常に変化しているので、変化の状況に応じて経営戦略を策定し、事業領域を再構築します。ちなみに、事業の再構築のことを英語で、Business Restracture(リストラ)と言います。リストラとは従業員を解雇することではありません。そして、経営戦略を実施するために、中期経営計画(2~3年の計画)を立案し、中期経営計画を基に、短期(半年~1年)の経営計画を立案します。
したがって、すべての業務は中期経営計画、及び経営計画を達成するために実施するのです。よって、各業務は、これらと結びついていなければなりません。
つまり、各業務は、中期経営計画、及び経営計画と整合していなければならないのです。よって、各業務の目的が中期経営計画、及び経営計画と結びついているかどうかをチェックする必要があります。
各業務の目的が、順次、個別業務(職務)⇒小分類業務⇒中分類業務⇒大分類業と、上位業務の機能になっていれば、業務の目的を果たしていることになり、最終的には経営計画を果たすことになります。その結果、経営計画が達成でき、売上や利益が増えることになります。逆に、各業務の目的が、経営計画に結びついていなければ、その業務は無用業務ということになります。
実際には、多くの企業では、各業務の目的が経営計画に結びついていないだけでなく、そもそも業務の目的がなかったり、目的が不明確だったりします。つまり、何のためにその仕事(業務)をしているのか分からないという場合が多いのです。
その主な原因は、目的を考えないで場当たり的に業務を指示したり、また、目的を確認しないで業務を実施したりするからです。
本来は、経営環境の変化により経営戦略を変更すれば、中期経営計画、及び経営計画を変更し、それに伴って各業務計画を変更して経営資源の効率的運用を図ります。つまり、現状業務を見直して、経営計画の達成に必要な新規業務を計画・立案したり、現状業務を強化したりして取り組みます。同時に、経営計画の達成に必要のない業務を廃止したり、削減したりします。要するに、中期経営計画、及び経営計画の変更に伴い、業務の入れ替えを行うのです。しかし、ほとんどの企業では業務の入れ替えをきちんと行っていないのです。
企業は経営環境の変化に適応し、リスクを冒して戦わなければ生き残ることはできません。このことは従業員にとっても同じです。これまで行ったことがない新規業務や新規事業に取り組まなければならないのです。よって、意識(考え方や価値観)を変える必要があるのです。
しかし、人は誰でもこれまでに培われた考え方や価値観を持っており、そこからなかなか抜け出せない思考の壁があるのです。そこで、これを自ら打ち破らなければなりません。そうしなければ人も企業も生き延びることができないのです。
無用業務を発見するためには、前回説明しましたように、まず、経営計画と大分類業務、中分類業務、小分類業務などの目的と機能がそれぞれ整合しているかどうかを確認します。もし、整合していなければ、その大分類業務、中分類業務、小分類業務などは不要となります。
本来は、経営計画を達成するために、大分類業務、中分類業務、小分類業務、及び各自の個別業務(職務)があるのです。そして、各自が行っている個別業務(職務)の機能を果たすために具体的な方法があるのです。これらの、「目的ー機能(役割)ー方法」の関係を確認することにより、「業務のあるべき姿と現状業務の実態とのギャップ」を明確にすることができます。
よって、必要業務が確認できるだけでなく、無用業務、過剰業務、重複業務などのムダな業務や不足業務が明確になるのです。つまり、ムダな業務や不足業務が発見できるのです。
また、前回説明しましたように、業務を上位から下位に向かって順にブレイクダウンしていくと、その機能(役割)は何か、さらにその下位の機能(役割)は何かという具合につながっています。そして、逆に下位から上位に向かってその目的は何か、さらにその目的は何かという具合につながっているはずです。
これらがうまくつながっていれば、問題ないのですが、通常、つながっていないためにムダな業務や不足業務が発見できるのです。つまり、目的のない業務や機能(役割)を果たしていない業務などが発見できるわけです。
なぜなら、本来は経営計画を達成するために業務を立案・設計するのですが、実際にはそうしていないからです。各社の業務分掌規程を見ると、経営計画とは関係なく、各部門の都合で業務を立案・設計し、実施している企業が多いです。
実際に、クライアント企業の各部門の部長クラスの人たちに聞くと、「経営計画は一応確認するが、数日で忘れる」と言っていました。
本来、経営環境の変化に対応するために経営戦略を策定し、経営戦略を実行するために事業領域を設定し、そして中期と短期の経営計画を立案し、経営計画を実行するために各部門の業務を計画して実施するわけです。つまり、
経営環境の変化⇒経営戦略の策定⇒事業領域の設定⇒中期経営計画の立案⇒短期経営計画の立案⇒各部門の業務計画の立案及び実施、となるわけです。
ところが、実際に業務効率化活動を行ってみると、大分類業務、あるいは中分類業務が不要と分かり、それに伴い、○○部が不要になったり、○○課が不要になったりした例が多くあります。よって、これによって、大幅に人員を削減しています。
例えば、法務部、教育部、市場調査部などが廃止されることは多くの大企業で見られます。これらの部門は、かつて必要があって設立した部門ですが、必要がなくなってもそのまま継続している場合が多いからです。また、一旦、廃止しても、必要になった時には外部の専門機関に委託した方が専門的知識・経験があるのでメリットが大きいからです。
また、前回説明しましたように、業務の目的と機能とは1対1ではありません。1つの目的を果たすためにいくつかの機能があり、逆に、いくつかの機能で1つの目的を果たしています。よって、目的と機能の関係を調べればムダな機能(業務)や不足する機能(業務)が発見できるのです。
また、既に説明しましたように、1つの機能を果たすためにいくつかの方法があります。現在の方法はそのうちの1つに過ぎません。したがって、もっと良い方法を探して改善できる可能性があるのです。IT化もそのうちの1つの方法にすぎません。IT化して業務スピードを速くすればよいのではありません。既に説明しましたように、安、安、正、速、楽の5つについて検討するのが創意工夫による改善です。
そもそも、すべての業務は何らかの目的を果たしていなければなりません。そうでなければ、時間(コスト)をかけて業務を行う意味がありません。それどころか、「目的のない業務を指示命令する」ということは、その業務を担当する人に対して人間性を否定することになるのです。
別の言い方をすれば、目的のない業務を部下にやらせるのは、殺人罪に値します。「そんな大げさな」と思った人は、実際に目的のない仕事を自分でやってみれば良く分かります。
例えば、江戸時代に、罪人に対する刑罰に、「目的のない仕事をやらせる」ことが最も重い刑罰としてあったそうです。
その刑罰は、例えば、地面に穴を掘って掘を作らせるのです。水が漏れないようにしっかりと作らせるのです。罪人は最初は打ち首と覚悟していたので、この刑罰を喜びます。よって、一生懸命に堀を作ります。まず、穴を掘ります。掘り終わったら石を敷き詰めます。石の上に砂利を敷き詰めます。その上に粘土を敷き詰めます。内側の壁も同じようにします。そして、水が漏れないような堀が出来上がったら、水を入れます。罪人は完成を喜び、これで家に帰れると思います。ところが、数日経って水が漏れないことを確認したら、次にその堀を埋めさせるのです。以前そこに堀があったことが分からないようにきちんと堀を埋めさせるのです。
堀がきちんと埋まったら、また、同じ場所に穴を掘って堀を作らせるのです。水一滴漏らさないような堀を作らせるのです。出来上がったら、又その堀を埋めさせるのです。これを何度も永久に繰り返すのです。
すると、ほとんどの罪人は数日で発狂するか自殺するそうです。しかし、その前に、ほとんどの罪人が、打ち首にして欲しいと懇願するそうです。しかし、それは絶対に許されません。打ち首の方が刑が軽いからです。どうですか、これでもあなたは目的のない仕事を部下にやらせますか。
目的のない仕事や何の役割も果たさない(何の役にも立たない)仕事を一生懸命に行うのはムダなだけではありません。ムダだと分かった時のことを考えて下さい。「俺はいったい何をしていたんだ」「こんなムダな仕事をするために何か月も努力をしてきたのか」と気が狂いそうになります。
実際に気が狂って自殺した人もいます。実は、いわゆる過労死の原因を調べてみると、単に、長時間労働で肉体的な疲労が頂点に達していたからというよりも、精神的な苦痛に耐えられなくなったのが原因です。当然でしょう。肉体的な疲労がどんなにひどくても、それだけで自殺する人なんていません。精神的におかしくなったからです。ムダな仕事を長時間やらせれば誰でも気が狂います。
しかし、実際には、多くの企業ではムダな仕事を平気で部下にやらせています。それは、その仕事がムダだということを知らないからできるのです。そこで、ムダな業務を指示・命令した人に、その業務の目的を明確にしてもらいます。そして、目的のない業務や目的が不明確な業務は直ちに廃止します。
Ⓒ 開発&コンサルティング