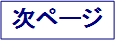
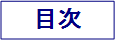
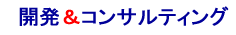
前回、明らかに価値のないムダな業務について廃止・削減の検討を行いました。次に、価値があると思われる業務について、本当に価値があるか無いかを調べ、もし、価値がなければ廃止・削減の検討を行います。
価値があると思われる業務は、計画・立案・設計と加工・編集・処理の業務です。これらの業務は売上や利益を増やしているはずなので、実際に売上や利益を増やしているか否かについて確認してみようということです。そこで、まず、各業務について目的と機能を確認します。
各業務は何のために行うのか(目的)、どのような機能(役割)を果たしているのかを確認すれば、売上や利益を増やす業務かそうではない業務かが分かるからです。実際にどのくらい売上や利益を増やしているかは詳細に調べてみなければ分かりませんが、売上や利益を増やす業務かそうでない業務かは、業務の目的と機能(役割)を確認すれば分かるからです。
通常、多くの人は、自分が行っている業務の目的や機能(役割)をあまり考えたことがないので、業務1つひとつについて改めて考えてみるのです。すると、多くの企業では、これといった目的がなかったり、目的が不明確だったりする業務が多く発見できるのです。
また、目的は明確だけれど、目的に対して機能(役割)を果たしていないとか、機能(役割)を果たすような内容(方法)になっていないなどの業務が発見できるのです。つまり、業務の目的に対して、実態が異なっている業務が多く発見できるのです。
これらの原因は、業務を指示する上司が目的や機能を明確にしないで指示するからです。また、業務を実施する担当者も目的や機能を確認しないで実施するからです。要するに、上司が場当たり的に業務を指示し、また、担当者が確認しないで実施するのが原因です。そのうえ、担当者は自分が好きな方法や容易な方法で業務を実施するからです。
本来、各業務は経営計画を実施するためにあるのです。そこで、クライアント企業で各業務と経営計画との関係を調べてみると、経営計画を実施するための業務になっていない場合が多いのです。つまり、
場合が多いのです。要するに、経営計画と各業務との整合性が図られていないのです。この原因は、部門長が何のために業務計画を立案するのかを知らないからです。業務計画は目先の課題を解決するためにあるのではありません。経営計画を実施するためにあるのです。
多くの企業では、経営計画と業務計画とは関係なく、別々に立案していたり、経営計画を無視して業務計画を立案したりしています。
実際に、クライアント企業で調べてみると、経営計画は経営者(社長、役員)が中心になって立案しているのに対して、業務計画は経営計画とは関係なく、各部門で目先の課題を解決するために立案しているのです。
そこで、クライアント企業の各部門の部門長に「経営計画についてどのように考えていますか」と聞いてみると、「経営計画は立案された時に、一応、内容を確認するが、数日後には忘れる」と言っていました。よって、明らかに経営計画とは関係なく、業務計画を立案して実施しているのです。
さらに、業務の担当者に「あなたの仕事は何ですか」と聞くと、仕事の内容(方法)はすぐに答えるのですが、「その仕事の目的は何ですか」と聞くと、ほとんどの人が答えられないのです。さらに、「その仕事の役割は何ですか」と聞いても答えられないのです。つまり、業務の目的や機能(役割)を知らずに業務を実施しているのです。実際に、このような企業が非常に多いです。
それだけではありません。経営計画を立案した経営者(社長や役員)ですら、経営計画を実施するために何をすれば良いのか、自分の役割は何かが分からないのです。つまり、経営計画の進捗管理を行っていないのです。経営計画を立案すれば、後は各部門で経営計画どおり業務を実施するはずだと経営者が考えているのです。
このような状況では、経営計画どおりに業務を実施できるわけがありません。経営計画が絵に描いた餅になっているのです。よって、業績も良くならないのです。
改めて、業務の目的と機能(役割)を明確にする理由を考えてみましょう。
業務の目的と機能(役割)を明確にすることによって、業務の本来の姿、つまり、あるべき姿が明確になるからです。業務は本来どうあるべきかということを、業務の目的と役割を確認することで明確になるのです。
業務のあるべき姿と現状業務の実態とを比較することにより、問題点が発見できるので、業務の改善・効率化、あるいは業務改革ができるからです。
業務はその目的と役割を果たすことによって業務価値が生まれるので、目的と役割をどの程度果たしているかを検証することにより、業務価値の高さが確認できます。そして、無価値・低価値の業務が発見できれば、業務の改善・効率化ができるわけです。
また、業務の役割を果たす方法を検討することにより、より良い方法を探したり、創意工夫によってより良い方法に変えたりすれば、より価値の高い業務に変えることができるのです。
さらに、業務のあるべき姿と現状業務の実態との比較から、新たに必要な業務(不足業務)が発見できるので、業務改革ができるのです。
以上の考え方は、VE(バリューエンジニアリング:価値工学)の考え方です。製品のコスト削減や新製品開発に用いるVEの考え方を業務に適用しただけです。その証拠に、以上の文章の「業務」を「製品・部品」に変え、「業務の改善・効率化」を「製品のコスト削減」に、「業務改革」を「新製品開発」に変えればそのままVEの説明になります。
よって、VEを学んだことがある人は、以上の考え方が容易に理解できると思います。なお、VEについて詳しくは、『文科系のためのコスト削減・原価低減の考え方と技術』に書きましたので参考にしてください。
ここで改めて、業務の価値について説明をしておきます。
前回は業務の価値を高めるために、価値のない業務を削減することについて説明しました。前回説明しました業務の価値は付加価値でした。しかし、ここで説明する業務の価値は付加価値ではありません。顧客価値です。
付加価値は企業が求める価値ですが、顧客価値は顧客が求める価値です。業務の目的と機能(役割)を検討する際には常に顧客の立場で考えなければなりません。なぜなら、本来、業務は企業のために実施するだけではなく、顧客のためにも実施するからです。
付加価値と顧客価値との関係を簡単に説明しますと、付加価値はその計算式から明らかなように、売上や利益を増やせば付加価値が高くなります。付加価値=売上-外部購入(支払)費用だからです。そして、売上や利益を増やすためには顧客満足を追求して、顧客価値を高くする必要があります。
このように考えると、付加価値と顧客価値は結果的に同じように見えますが、コストを計算する際には異なります。企業の立場でコストを計算するか、顧客の立場でコストを計算するかです。
顧客の立場でコストを計算すると、企業の立場で計算した時には分からなかったムダなコストや不足するコストが発見できます。つまり、ムダな業務や不足する業務が発見できるのです。
価値の高い業務とは、目的と機能(役割)をきちんと果たしている業務のことを言いますが、それに対して、
(1)価値のない業務とは、目的と機能を全く果たしていない業務であり、文字どおり、無価値業務です。無価値業務は無用業務、不要業務などとも言います。
(2)価値の低い業務とは、目的と機能の果たす度合が低い業務です。言い換えれば業務品質が悪い業務です。これを低価値業務と呼びます。
(3)過剰業務とは、価値はあるが必要以上に時間(コスト)をかけている業務を言います。つまり、業務時間(コスト)が過剰となっている業務です。言い換えれば、投入と得られる効果を計算した時に、効果の割に投入が大きい業務です。時間(コスト)をかけ過ぎている業務は、企業にとっても顧客にとっても損失になります。その時間(コスト)を別の業務に使うべきです。
なお、過剰業務は、「4-4 業務の目的別・機能別原価計算」で業務コストを計算して判定します。業務の目的別・機能別コストは顧客の立場で計算したコストです。これに対し、通常行われている原価計算の方法で計算した業務別コストは企業の立場で計算したコストです。企業の立場で業務別コストを計算しても、ムダなコストかそうでないコストかが分からないので何の役にも立ちません。
(4)重複業務とは、目的と機能が同じ業務、又は類似している業務を言います。別の人が別の方法で業務を行っている場合には、目的と機能が同じ、又は類似していることが良くあります。お互いに知らずに重複して行っているのです。よって、重複業務も無価値業務です。
なお、以上の業務の価値はVEによる価値概念です。また、目的別・機能別原価計算はVEにおいては、顧客が求める製品の価値を高めるために、製品のコスト削減や新製品開発を行う際の原価計算方法です。つまり、VEでは製品の材料別、部品別のコスト計算ではなく、目的別、機能別のコスト計算を行います。目的別、機能別のコストを計算することにより、顧客の立場でコスト計算ができるので、ムダな材料、ムダな部品、不足する材料、不足する部品などが発見できるのです。
このVEの価値概念、及び原価計算の方法をそのまま業務に適用するのです。そうすれば、業務の効率化や業務改革ができるのです。つまり、VEの考え方や方法を適用する対象を製品から業務に変えるのです。そうすれば、製品のコスト削減が業務の効率化になり、新製品開発が業務改革になるのです。
(5)ネック業務とは、業務フローの中で最も時間(コスト)がかかっている業務を言います。ネック業務に時間(コスト)がかかっていれば、結果的に、業務フロー全体がネック業務と同じ時間(コスト)かかっていることになります。このために、ネック業務を探して時間(コスト)削減を行うのです。この考え方はIEの考え方です。たとえ個々の業務をIT化して時間短縮を図っても、ネック業務に多くの時間(コスト)がかかっていれば何もなりません。
Ⓒ 開発&コンサルティング