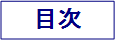
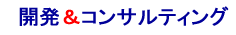
本章からは業務改革の説明になりますので、まず、業務改革を通じて経営の骨組みを再構築する目的(理由)について説明いたします。
経営の骨組みとは、経営を行うのに必要な基本的な仕組みであって、経営理念、経営戦略、事業領域(ドメイン)、中期経営計画、経営組織、人事制度などを言います。これらを見直し、再構築することによって、間違いのない業務改革ができるわけです。骨組みがしっかりできていれば、肉付けは各社の状況に応じて行えば良いのです。
多くの企業では、業務改革の目的は業務発生の源である「中期経営計画の達成」にする場合が多いです。しかし、多くの企業では中期経営計画が達成できないのです。その理由を一言で言えば、経営の骨組みができていないからです。
そもそも、中期経営計画を達成する目的は何でしょうか。それは、既に説明しましたように、経営環境の変化に適応するためです。このために、経営戦略を策定し、事業領域(ドメイン)を見直して中期経営計画を立案したのです。
経営環境の変化⇒経営戦略の策定⇒事業領域の見直し⇒中期経営計画の立案
したがって、中期経営計画の立案は経営戦略を実行するためでもあります。つまり、中期経営計画は経営戦略の実行計画なのです。中期経営計画は経営戦略と事業領域を基に立案します。よって、これらが中期経営計画立案の根拠となりますので、中期経営計画を達成するためには、まず、これらの根拠を確認する必要があります。
しかし、多くの企業では、そもそも経営戦略や事業領域(ドメイン)さえ明確にしていないのです。あるいは、これらを明確にしていても、経営環境の分析に基づいていない企業もよくあるのです。
本来、経営戦略や事業領域(ドメイン)は経営環境の変化に応じて変えなければならないのですが、ほとんどの企業では経営環境の変化に適応できていません。なぜなら、そもそも経営環境の分析を行っていないためです。
しかし、経営環境を分析し、経営戦略や事業領域を策定し、また見直すだけではダメなのです。中期経営計画を達成するためには、経営組織、人事制度などを見直しする必要があるのです。なぜなら、多くの企業では経営組織や人事制度が中期経営計画を実施できるようになっていないからです。
また、多くの企業では中期経営計画そのものを見直しする必要もあります。なぜなら、中期経営計画があまりにも理想的で企業の実態とかけ離れている場合があるからです。要するに、中期経営計画が絵に描いた餅なのです。このような形だけの中期経営計画では実施できません。
その理由として、中期経営計画を実施するための経営資源が不足している場合があります。つまり、人材がいないとか、資金がないとか、技術がないとかがあります。したがって、経営資源に合わせて中期経営計画を立案する必要があります。
経営環境は常に変化しているわけですから、経営環境の分析を定期的に行い、経営環境の変化に対応した経営戦略、事業領域、中期経営計画、経営組織、人事制度などを構築し、それらを基に経営を行う必要があるのです。
よって、経営の骨組みの見直しを行って、再構築する必要があるのです。そこで、業務改革活動を通じて経営の骨組みを再構築するのです。
経営の骨組みを再構築するもう1つの目的は、間違った意思決定によってムダな業務を指示命令したり、ムダな業務を実施したりしないようにするためです。経営環境が変化しているにもかかわらず、従来の経営の骨組みのままであれば、当然、間違った意思決定を行ったり、間違った業務を指示命令したりするからです。
また、業務効率化の説明で既にお分かりのように、業務の目的や機能を確認しないために、ムダな業務を指示命令したり実施したりしてしまうのです。新規業務や新規事業を計画する場合にも、業務の目的と機能を明確にして計画しなければなりません。そうしなければ、また、ムダな業務を指示命令したり、実施したりすることになるのです。
多くの企業では新規業務や新規事業を計画する場合に、経営戦略や事業領域(ドメイン)に基づくのではなく、経営者・管理者の経験や希望に基づき計画しています。つまり、経営者・管理者がこれまでの経験に基づき、実施してみたい新規業務や新規事業を計画するのです。したがって、どうしてもムダな業務が入り込んでしまうわけです。
そこで、新規業務や新規事業の計画をする場合には、経営者や管理者の経験や希望に基づくのではなく、経営戦略や事業領域(ドメイン)の基で、新規業務や新規事業の目的との整合性を確認しながら計画するようにします。
つまり、経営戦略の実行計画である中期経営計画の内容が新規業務や新規事業などの目的に一致する必要があります。つまり、
経営戦略の内容=中期経営計画の内容=継続業務、強化業務、新規業務、新規事業などの目的
です。したがって、中期経営計画をブレイクダウンした経営計画に基づき、各部門で業務設計を行い業務計画を立案して実施すれば、中期経営計画が確実に実施でき、また計画どおりに達成できるのです。しかもムダな業務を指示命令したり、実施したりすることがなくなるのです。つまり、
中期経営計画⇒経営計画⇒業務設計⇒業務実施
によって、中期経営計画が確実に実施でき、計画達成できるのです。
経営の骨組みを再構築する最も重要な目的は、イノベーションを実施できるようにするためです。昨今では、世界的な競争が激化しているため、企業はイノベーションを実施しなければ競争に勝てなくなっているのです。欧米の経営戦略論の結論は「イノベーションが実施できなければ、今後、企業は生き残ることが出来ない」です。そのため、各国の企業はこぞってイノベーションに取り組んでいるのです。(参照:『経営戦略全史』三谷宏冶 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン出版)
しかし、日本の企業はイノベーションが実施ができないのです。それは集団主義により、従来から個人の都合より会社の都合(決定)を優先し、個人の考え方や価値観を尊重しないためです。
例えば、日本の企業の意思決定は、いわゆるボトムアップ方式、あるいはミドルアップダウン方式により、組織を通じてみんなで意見を出し合い、合議制(多数決)によって意思決定を行います。そして、みんなで協力して一致団結して実行するのです。要するに、みんなで決めて、みんなで実行するのが日本の経営のやり方なのです。
その結果、みんなが賛成するような、できるだけリスクを冒さない無難な案(戦略、計画)に決まるのです。たとえ経営者がリスクを冒してイノベーションを実施しようとしても反対する人が多く、イノベーションが実施できないのです。トップダウン方式ではないからです。このため、アメリカの戦略家であるマイケル・ポーターに「日本の企業はオペレーション効率は高いが、戦略を持っている企業はまれである」と言われてしまうのです。(参照:『日本の競争戦略』マイケル・ポーター著 ダイヤモンド社)
また、日本の企業はイノベーションが実施できるような経営組織や人事制度になっていないのです。集団主義により、個人の能力よりも会社の都合(決定)を優先するからです。また、成果給ではなく、年功給、時間給、日給、月給などになっているため、保有する能力を発揮して働こうとする意欲が湧かないからです。つまり、失敗するリスクを冒してまでイノベーションを実施しようする社員がいないのです。
本来、イノベーションを実施するのは会社(集団)ではなく、個人(社員)なのです。よって、欧米のように、個人主義に基づく戦闘集団に変える必要があります。このため、イノベーションを実施できるような経営組織や人事制度に変える必要があるのです。
そもそも日本の企業は、開発や改革が得意ではありません。日本の企業が得意なのは改善(KAIZEN)であって開発や改革ではないのです。まして、イノベーション(革新)ではありません。イノベーションが必要な今日でさえ、従来の得意な改善・効率化技術を活用して戦おうとしているのです。つまり、既にある製品の品質向上、コスト削減、生産の効率向上、業務の効率化など、改善・効率化技術を活かせば競争に勝てると信じているのです。
しかも、最近の改善・効率化技術はアメリカが開発したものばかりです。例えば、インターネット、IT、AIなど最近の改善・効率化技術はすべてアメリカが開発したものです。そして、日本はこれらの改善・効率化技術を使って、既存製品の品質向上、コスト削減、生産の効率化、業務の効率化などに取り組んでいるのです。
分かりやすく言えば、現在世の中にある製品や商品、サービスなどを、より低価格に、より高品質に、より高機能に、より高付加価値に改善したり、現在行っているいろいろな作業、業務などを、より安全に、より安く、より速く、より楽にして効率的にするために、インターネット、IT、AIなどを活用しているのです。
このような改善・効率化技術はいつの時代でも必要ではありますが、現在、世界はイノベーションの競争になっているのです。日本が既存製品の改善や既存業務の効率化などに取り組んでいる間に、世界では画期的な新製品を開発したり、画期的な新事業を開発したり、画期的な新技術を開発したりして、既存の製品や業務、既存の事業や技術を不要にしてしまうのです。
ちなみに、P.F.ドラッカーも、「イノベーションと企業家精神にとっての障害は、既存の事業であり、特に成功している事業である」と書いています。いつまでも得意な改善・効率化ばかりに取り組んでいると、足をすくわれることになります。画期的な新製品や新事業の開発、新技術の開発などのイノベーション(革新)に取り組まなくては生き残ることは出来ないのです。
Ⓒ 開発&コンサルティング