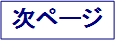
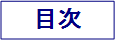
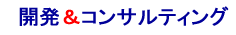
業務効率化(ムダな業務の廃止・削減)活動は経営者(社長、役員)が参加しないと成功しません。なぜなら、経営者(社長、役員)の考え方・価値観が変わらなければ業務効率化(ムダな業務の廃止・削減)はできないからです。
なぜなら、ほとんどの業務は経営者(社長、役員)の指示・命令に基づいて行われるからです。したがって、ムダな業務を指示・命令しているのも経営者(社長、役員)ですし、これによって業績を悪化させているのも経営者(社長、役員)なのです。
なお、経営者の指示・命令によらない業務もあります。部門長や課長、係長などが独自に指示・命令した業務、法律に基づく業務、業界組合の規定に基づく業務、取引先や顧客から要求された業務などです。しかし、これらの業務も基本的には経営者の考え方(経営方針など)に基づいて指示・命令したのです。
ムダな業務を廃止・削減する活動の進め方は、通常、ボトムアップ方式で行います。すなわち、準備作業が終わった後に、順次、各段階でムダな業務を削減していきますが、各段階では以下のようなステップで進めます。なお、各段階と言うのは、序文で書いた業務効率化の進め方の各段階のことです。
よって、経営者(社長、役員)が参加しない場合は役員会においてムダな業務の削減検討を行わないないわけですから必ず失敗します。その理由は最初に書いたように、ムダな業務を指示・命令しているのは経営者(社長、役員)だからです。
ここで、まず、失敗する企業の事例を紹介しましょう。1つは、業務効率化活動の始めのうちは、社長も役員も活動を積極的に推進するのですが、活動が進むに従い、社長や役員の考え方・価値観に問題があることが分かり、このことを隠すために途中で活動を中止したり、あいまいに終わらせてしまったりするのです。
もう1つは、活動の途中から社長や役員は参加しなくなり、そのまま部門長以下で最後まで活動を実施する場合です。これは、社長や役員にとっては都合の良い方法です。つまり、部門長以下が指示した業務だけを対象に業務効率化活動を行うわけです。そして、各部門でムダな業務を廃止・削減し、部内の人員削減を行うのです。
この場合に失敗する原因は、第1に、社長や役員が指示した業務は効率化の対象にならないわけですから、業務効率化がほとんどできないからです。部門長以下が独自に指示したムダな業務は、ホワイトカラーの業務量の10%以下に過ぎません。つまり、業務効率化の成果が10%以下になってしまうのです。
第2に、どの部門も自部門だけは人員削減したくないですから、業務の効率化をしようとしないからです。部門ごとに何人、あるいは何パーセントの人員削減を行う、と目標を決めて行う場合もありますが、どの部門も人員削減したくないですから目標が決まらないのです。
そこで、強制的に削減目標を一律〇〇パーセントとする場合がありますが、もともと適正人数が決まっているわけではないので不公平になってしまいます。また、効率化の成果に比例して人員削減しようとすれば、当然、どの部門も効率化しなくなります。
第3に、これが最も大きな失敗原因となりますが、社長や役員の考え方・価値観が変わらないからです。たとえ、活動が無事に終了し、一時的、かつ部分的に効率化ができたとしても、すぐに元の状態に戻ってしまうのです。
なぜなら、社長や役員が指示した業務のうち、何がムダで何がムダでないかを明確にしない限り、ムダな業務は何度でも指示されることになるからです。ですから、社長や役員の考え方・価値観が変わらないとダメなのです。したがって、経営者が参加しない業務効率化活動は必ず失敗します。
次に成功する事例を紹介します。まず、社長がリーダーシップを発揮して最後まで積極的に活動を行う場合は間違いなく成功します。例えば、社長自身が自ら指示した業務を見直してムダな業務を廃止・削減するのです。
社長が積極的であれば他の役員も部門長たちも積極的にならざるを得ないでしょう。そうすれば、当然、全社一丸となって業務効率化活動を推進することになります。実は、このような会社は一部上場企業に多いです。このため、一部上場企業では全業務量の30%以上の業務効率化ができるのです。
それは、一部上場企業に限らす、大企業のほとんどの社長がサラリーマン社長だからではないでしょうか。業績が悪化すれば最終的には社長の責任となりますから、業績を上げるために積極的に活動を推進しようとするのです。
ところで、コンサルタントの話は、活動の考え方や進め方以外は先進企業の事例紹介ですから、他社でどのように業務を行っているかが具体的に分かるわけです。したがって、参考になる事例が多いはずです。
コンサルタントの役割はひと言で言えば提案と助言ですが、提案と助言ができるのはいろいろな企業でコンサルティングを実施した経験があるからです。早い話が、先進企業から学んだものを他の企業に伝えているだけなのです。ただし、公開された事例、あるいは公開の許可を受けた事例だけです。他社の先進事例を多く知れば知るほど、社長の考え方・価値観が変わる可能性があるのです。
ただし、他社の先進事例はあくまで事例であって、自社にそのまま当てはまるわけではありません。よく、他社事例をそのままマネしようとする会社がありますが、それは絶対にできません。自社と他社では、経営環境、経営戦略、事業領域などが違いますし、人・モノ・金・技術・情報・文化などの経営資源も異なるからです。
自社の業務の効率化は自社で創意工夫しなければできません。まして、業務をIT化しただけでできるわけがありません。業務効率化に成功した企業は、経営者だけでなく、従業員全員が効率化の考え方と進め方を基に、自社に合った方法を創意工夫した企業だけです。
Ⓒ 開発&コンサルティング