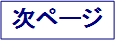
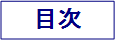
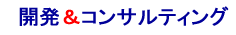
今回は、まず、VVEの基本的考え方について説明いたします。そのうえで、VEの「おかしな考え方」「間違った考え方」について、<VEとの違い>で説明いたします。
さて、顧客は、製品を購入しようとする時に、製品そのものが欲しいと言うよりも、その製品から得られる効用(便益)が欲しいのです。
例えば、顧客が扇風機を購入しようとする時に、扇風機そのものが欲しいと言うよりも「涼しい風」が欲しいのです。扇風機を購入し、使用すれば、涼しい風が得られるからです。
よって、効用(便益)を得ようとすることは製品の購入目的であり、製品の使用(利用)目的です。
そして、この効用(便益)は、その製品が備えている機能(役割、働き)を果たすことによって生まれます。
例えば、扇風機が「風を発生する」という機能を果たすことによって効用(便益)が生まれるのです。したがって、
顧客は製品を購入するのではなく、製品が備えている機能を購入するのです。
このように、扇風機の目的は「人を涼しくする」であり、機能は「風を発生する」です。よって、製品の目的と機能を確認することは最も重要なことなのです。
そして、顧客は、機能がきちんと果たされるか否かによって製品価値があるか無いかを判断します。例えば、風を発生しない扇風機は(壊れているので)製品価値がないと判断します。
また、顧客は機能が果たされる度合い、すなわち機能の達成度、によって製品価値の高さを判断します。
例えば、弱い風しか発生しない扇風機よりも、強い風を発生する扇風機の方が、製品価値が高いと判断します。なぜなら、強い風を発生する扇風機の方がより涼しくしてくれるからです。つまり、効用が大きいからです。
このように、製品価値の高さは製品が備える機能の達成度で測られます。例えば、扇風機の価値の高さは「風を発生する」という機能の達成度、すなわち最大風速又は最大風力で測られます。また、製品価値の高さは顧客が求める効用の大きさ、又は、得られる満足度で判断されます。すなわち、
製品価値の高さ=機能の達成度=効用の大きさ=顧客満足度
となります。そして顧客は、製品を購入するときに、製品価値と価格とを比較して、どちらが高いかを検討し、その製品を購入するか否かを決めます。
当然、顧客は製品価値が価格より高くなければ購入しません。すなわち、製品価値>価格でなければ購入しません。
よって、企業は価格より価値の高い製品を製造・販売しなければ売れません。また、価格より安いコストで製造・販売しなければ利益が得られません。
以上の考え方がVVEの基本的な考え方ですが、ごく自然の常識的な考え方であると思います。常識的な考え方を少し理屈っぽく説明しました。
以上のVVEの基本的な考え方を式で表すと以下のようになります。
V:Value F:Function P:Price C:Cost
(1)式は、製品価値は機能に比例するという式です。製品価値の高さ=機能の達成度ですので、製品価値と機能は比例するのです。製品が備える機能を果たすことによって効用が生まれ、それが製品価値となります。製品に必要な機能が備えられており、且つその機能が充分に果たされれば効用が大きくなるので製品価値は高くなります。しかし、機能が不足していたり、機能が充分に果たされなければ効用が小さくなるので製品価値は低くなります。つまり、製品価値と機能とは比例するのです。
(2)式は、製品価値は価格より高く、コストは価格より安い、という式です。製品価値が価格より高くなければ顧客は製品を購入しませんし、コストが価格より安くなければ企業は利益を得られない、ということを表した式です。価格は企業が決めますが、基本的には需要と供給の関係で市場で決められるので、企業は価格より価値の高い製品を、価格より安いコストで製造・販売しなければならないということです。
これらの式は極めて常識的で誰もが理解できる式だと思います。これらは単純な式のように思えますが、実は重要な式です。なぜなら、これらの式が成り立たないと、製品の存在価値も、企業の存在価値もなくなってしまうからです。
このVVEの基本的考え方を始め、すべての考え方や技術、あるいは進め方はこのように常識で成り立っていますので、その内容も容易に理解できるものと思います。
なお、VVEの改善・開発対象は、製品の他に、サービス、業務、仕組み、システム、組織、企業などいろいろありますが、ここでは製品を例にして説明しております。よって、ここで説明している考え方はどの対象にも当てはまる考え方です。
ちなみに、経済学では製品(商品)やサービスを顧客が消費することによって得られる満足を効用(ユーティリティ)といい、経営学では便益(ベネフィット)と呼んでおります。
VEの基本的考え方はVVEとは全く異なるものです。そこで、まず、VEの基本的考え方について説明し、そのうえで、VEの基本的考え方が「おかしな考え方」「間違った考え方」であることを説明したします。
VEを学んだことがある人は、VEの基本的な考え方をご存じだと思います。日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE基本テキスト』には次のように書かれています。
顧客が物を買う場合に、その代価を支払う。大きな働きを期待する場合には、多くの代価を支払うし、期待する働きが小さければ、支払う代価も少ない。また、同じ働きをするならば、その代価は、安ければ安いほど、望ましいことになる。つまり、その“もの”の働き(機能)と、それに支払う代価(顧客にとってはコスト)との比によって、価値の大きさが測られることになる。
VEでは、その関係を、次の式で表す。
価値(指数)=顧客の要求する機能の達成度合÷取得して使用するための費用(コスト)
または、
VALUE(価値指数)=FUNCTION(機能)÷COST(費用)
すなわち、顧客の要求する働き(機能)に対し、費用を安くするか、あるいは、同じ費用で働き(機能)を大きくして、その価値を高めることを研究するのが、VEであるといえる。
以上のように書かれているのですが、まず、用語について確認しておきます。価値の大きさを測るのに「価値(指数)」又は「価値指数」と言う用語を使っています。最初の式は、価値(指数)と書かれていますが、価値(価値指数)でしょう。
また、ここで使用している費用(コスト)は、顧客が支払う代価ですから、価格のことです。
よって、価値指数=機能(働き)÷代価(価格)となります。
次に、ここに書かれている文章、及び関係式について検討してみます。最初に、「顧客が物を買う場合に、その代価を支払う。大きな働きを期待する場合には、多くの代価を支払うし、期待する働きが小さければ、支払う代価も少ない。」と書かれています。
次に、「また、同じ働きをするならば、その代価は、安ければ安いほど、望ましいことになる。」と書かれています。
そして、結論として、「つまり、その“もの”の働き(機能)と、それに支払う代価(顧客にとってはコスト)との比によって、価値の大きさが測られることになる。」と書かれているのです。
上の文章をもう1度読んでみてください。おかしいと思いませんか? 顧客は価値の大きさを0.8だとか1.2だとかと比によって測ることがありますか?
読者の皆さんは何か買い物をするときに、製品(商品)価値の大きさを比で測ったことがありますか。
例えば、この自動車の価値は1.5だとか、このパソコンの価値は0.8だとか、この魚の価値は0.9だとか、この肉の価値は1.3だとかと比で測ったことがありますか。筆者は生まれて以来、そのようなことは1度もありませんし、そのような人は私の周囲にはおりません。また、私が知っているVEの専門家(CVS:国際VEスペシャリスト)数人に尋ねても、そのような人はひとりもおりませんでした。
通常は、「この商品はどのくらいの価値があると思いますか」と人に尋ねた時に、人は、「〇〇円ぐらいの価値があると思います」と答えます。つまり、通常は、製品(商品)価値は価格で測る(表す)のです。比で測る(表す)ことはありません。
このように、VEでは実際にはあり得ないことが、当然、あるかのように書かれているのです。これは明らかに「おかしい」のです。
また、日本バリューエンジニアリング協会発行の『VE用語の手引き』には、次のように書かれています。「使用者は、製品やサービスを入手しようとする場合、それらが果たす機能と取得し享受するためにかけるすべてのコストとの比(価値の程度と呼ぶ)に基づいて、取得するかどうかを決める」と。
ここに書かれているコストとは、使用者が製品やサービスを入手する場合のコストですから価格のことです。
よって、価値の程度=機能÷価格
となります。ここでまた、用語について確認しておきます。VEでは価値の高さを測るのに、「大きさ」と言ったり、「価値指数」と言ったり、「価値の程度」と言ったりして統一しておりません。そのうえ、価値の高さは比で測るというのです。
一体、VEにおける価値とは何なのでしょうか。
本来、価値は高さと言うべきです。なぜなら、価値は大きいか小さいかではなく、高いか低いか、だからです。よって、価値は、「大きさ」でも「価値指数」でも「価値の程度」でもなく、価値は「高さ」です。VEでも「価値を高めることを研究するのが、VEであるといえる。」と書いています。
また、価値は比で測るものではありません。その理由を説明します。VEの基本的考え方を示した式、
価値(価値指数)=機能(働き)÷代価(価格)
は、「価値は機能(働き)に比例し、代価(価格)に反比例する」という式です。価値は機能に比例しますが、価格に反比例することはありません。
なぜなら、「価格が高い製品(商品)は価値が低く、価格が安い製品(商品)は価値が高い」などということはないからです。これを読みかえれば、「価値が低い製品(商品)は価格が高く、価値が高い製品(商品)は価格が安い」となりますが、どちらにしてもこのようなことはないのです。通常は、「価値が高い製品(商品)は価格が高く、価値が低い製品(商品)は価格が安い」のです。
しかし、だからと言って、価値と価格とが比例するわけではありません。価値と価格とは比例も反比例もしません。価値と価格とは何の関係もないのです。
なぜなら、そもそも、製品(商品)に価値があるか無いか、あるいは価値が高いか低いかは顧客が決めることだからです。また、価格は企業が決めるとしても、基本的には市場の需要と供給の関係で決まるからです。
だからこそ、顧客は価値と価格とを比較してどちらが高いかを見定めるのです。つまり、その製品(商品)の価値は価格より高いのか、低いのか、あるいは価値は価格に見合っているのかを見定めるのです。そして、その製品(商品)を買うか買わないかを決めるのです。
また、同じ製品(商品)であれば、価格が高くても安くても製品(商品)価値の高さは変わりありません。つまり、同じ製品(商品)を異なる価格で販売していても製品(商品)価値の高さに変わりはないのです。なぜなら、同じ製品(商品)だからです。
ところで、VEではジョブプラン(活動ステップ)の中に機能評価というステップがあります。機能を評価することによって製品価値の高さを測定するというステップです。
しかし、実際には、機能を金額で正しく評価するのは難しいので、対象とする製品と同じ機能を備えている最も安い他の製品(代替品)を探し、それぞれの代価(価格)を比較し、製品価値の高さを指数化しています。
例えば、対象とする製品の価格が2,500円で、同じ機能を備えている最も安い代替品の価格が2,000円だとすると、
価値指数=代替品の価格(機能評価値)÷対象製品の価格
ですので、機能評価値=2,000円、価値指数=0.8となります。
これについて日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE基本テキスト』には次のように書かれています。
「機能の値打ちを金額で見積って評価値を求めるには、対象の機能と、同じ働きをする最も安い代替品を探し、そのコストを評価値とする」「これによって、それぞれの機能ごとの価値指数が算出され、価値の大きさが明らかにされる。従って、価値指数が1より小さい場合や、他に比べて小さい場合は、それだけ改善の余地や、必要性が大きいことを示している」と。
ここでまた、新しい用語がでてきました。「機能の値打ち」という用語です。アメリカ国防総省が出版した『新版・価値分析ハンドブック』には次のように書かれています。
「値打(Worth)とは、使用者が必要としている機能を提供するために必要な最低の費用のことである。」と。
『VE基本テキスト』にも書かれているように、機能の値打とは同じ機能を備えている最も安い代替品のコスト(代価)のことで、VEでは機能評価値と言っています。代替品は対象製品と同じ機能を備えている他社の製品ですので代価(価格)は分かります。
つまり、VEでは価値の高さ(価値指数)を、
価値指数=F(機能)÷C(顧客が支払う代価:価格)
で表しているので、価値の高さ(価値指数)を測るために機能を評価するのです。そして、機能の評価の方法として、対象製品と同じ機能(働き)を備えている最も安い代替品を探し、その代価(価格)を機能の評価値とするのです。また、改善の余地を発見するために、価値指数が1より小さい代替品を探すのです。
ところで、日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE用語の手引き』には次のように書かれています。
「まず必要な機能のあるべきコスト=機能評価値とその機能を達成するために払われている現行コストを求める。この両者の差、ならびに両者の比によって算出した価値の程度をもとに・・・」と。
つまり、価値の程度とは、あるべきコストと現行コストとの差、又は比だと言うのです。一体どちらなのでしょうか。差でしょうか、それとも比でしょうか。
また、VEの基本的考え方を示した式、「価値指数=機能÷コスト(代価)」はジョブプラン(活動のステップ)の中では機能評価のステップのときにしか用いません。しかも、この機能評価の目的は、コスト削減や改良・開発の活動を行うか否か、あるいは活動の取り組み順序や取り組み範囲を決めるためなのです。つまり、活動の効率化のために用いるだけなのです。
なぜなら、対象製品の価値指数が1.0未満であればコスト削減や改良・開発の余地があると判断し、また、代替品の機能ごと(部品ごと)の評価値の高さによって取組順序や取組範囲を決めるからです。なお、代替品の部品ごとの機能は代替品を分解して見積りするしかありません。
すなわち、VEにおける機能評価の目的は、「顧客の立場で機能を評価する」という本来の機能評価のためではないのです。
ちなみに、VVEではもちろん、顧客の立場で機能を評価しますので、製品(商品)価値の高さは顧客にも分かります。なぜなら、既に説明しましたように、
製品価値の高さ=機能の達成度=効用の大きさ=顧客満足度
ですから、製品価値の高さは機能の達成度を測定すれば良いからです。扇風機の例で言えば、「風を発生する」という機能を評価するには、最大風力、あるいは最大風速を測定すれば良いからです。そして、製品の取り扱い説明書に測定結果を書いておけば良いのです。また、実際に扇風機のスイッチを入れて風を発生させてみれば風の強さがどのくらいか顧客にも分かります。
製品価値の高さが顧客に分からなければ、価値が価格より高いのか、低い(安い)のかは分かりません。ただし、製品(商品)によっては使用(消費)してみなければ分からない場合もあります。
ところで、VEではなぜ、価値指数=機能÷コスト(代価)としたのでしょうか。それは、アメリカ国防総省が「価値の公式」と定めたからです。アメリカ国防総省が出版した『新版・価値分析ハンドブック』には次のように書かれています。
「価値(Value)とは、与えられた状況下で使用する者(顧客)がその必要性と資源との面から眺めた値打とコストとの関係である。値打とコストとの比が価値の主要尺度である。したがって、価値指数(Value Index)を求めるために、次の“価値の公式”を使うことが出来る。
価値指数=値打÷コスト」と。
つまり、機能の値打と対象製品とのコスト(代価)の比を価値指数としているのです。よって、VEの基本的考え方がおかしい原因は、アメリカ国防総省が、機能の値打とコスト(代価)との比が価値の主要尺度であるとして、価値の公式と定めたからです。
しかし、VA(VE)の創始者であるL.D.マイルズ氏は、価値をこのような式では表現しておりません。また、「価値指数」と言う言葉も使っておりません。ところが、L.D.マイルズ氏の著書である『VA/VEシステムと技法』には、次のように書かれております。
「価値はコストを下げることにより(もちろん、性能は維持して)つねにあがる」と。
VEが理解できない原因はこの考え方にあると筆者は思います。なぜなら、マイルズ氏の考えである「価値はコストを下げることにより常に上がる」というのは常識では理解できないからです。「コスト(または価格)が安いほど価値が高い」のでしょうか? あるいは「コスト(または価格)が高いほど価値が低い」のでしょうか? そんなことはありません。
以上のように、VEは基本的な考え方が常識では理解できないだけでなく、用語の定義が曖昧であるのもVEを混乱させる原因です。これらを正してVEの優れた考え方や技術を分かりやすくして、多くの企業で活用すべきだと筆者は思います。
また、VEでは、価値指数=機能÷コスト(代価)にこだわるために、十分な成果が得られないのです。なぜなら、価値指数が1より小さい代替品を探すことができなければ、改善・開発を行わないからです。そのうえ、この式はVEの基本的考え方を示した式であるにもかかわらず、改善活動を効率的に進めるためだけに使うからです。
ところが、VEは優れた改善・開発技術です。このため、劇的な効果を生むのです。そこで筆者は、VEが常識では理解できないところは排除し、また、VEの専門家(CVS:国際VEスペシャリスト)でも理解できないところは修正・改善すると共に、VEの優れたところをより発展させてVVEを開発したのです。
そこで次回から、VVEのいろいろな考え方を詳しく、分かりやすく説明し、また、VEとの違いを説明いたします。ただし、VVEの考え方はすべて常識的ですので容易に理解できるものと思います。
Ⓒ 開発&コンサルティング