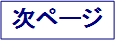
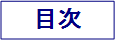
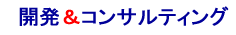
今回はVVEの定義と目的と機能について説明いたします。VVEの定義と目的と機能はVEと全く同じです。なんだ、などと言わないでください。VEそのものがVEの定義と目的と機能に合っていないから問題なのです。
そこで、今回は、まず、VEの定義と目的と機能について確認いたします。そのうえで、順次、数回にわたってVEそのものがVEの定義と目的と機能に合っていない「おなしなもの」であることを説明したいと思います。
日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE用語の手引き』には、「VEとは、最低の総コストで、必要な機能を確実に達成するために、組織的に、製品、またはサービスの機能の研究を行う方法」と書かれています。これがVEの定義ですが、その内容を見るとVEの目的と機能が書かれています。すなわち、VEの目的は、「最低の総コストで必要な機能を確実に達成する」ことであり、機能は、「組織的に、製品、又はサービスの機能の研究を行う」ことです。
また、同じ『VE用語の手引き』には、「VEの究極のねらいは、使用者の立場に立って、製品やサービスの価値に関する問題を研究し、価値の程度を高めることにある」と書かれています。つまり、「VEの究極のねらいは、使用者の立場で、製品やサービスの価値を高めること」です。この究極のねらいをVEの本来の目的、あるいは上位の目的と捉えることができます。すなわち、VEの本来の目的(上位の目的)は「使用者の立場で、製品やサービスの価値を高めること」です。
したがって、VEは価値向上の技術なのです。そして、VVEはこの定義と目的と機能に忠実な技術です。VE以上に忠実な技術です。少しでもこの定義と目的と機能に合わないものは断固排除するものです。
さて、改めてVEの目的と機能を整理すると、VEの本来の目的(上位目的)は、「(顧客の立場で)製品やサービスの価値を高める」ことであり、目的は、「(最低の総コストで)必要な機能を(確実に)達成する」ことであり、そのための機能は、「(組織的に)製品やサービスの機能の研究を行う」ことである、ということになります。かっこ書きの部分は条件です。
よって、条件の部分を除くと、VEの本来の目的(上位目的)は、「製品やサービスの価値を高める」ことであり、目的は、「必要な機能を達成する」ことであり、機能は、「製品やサービスの機能の研究を行う」ことである、という関係になります。本来の目的は上位の目的と考えられますので、
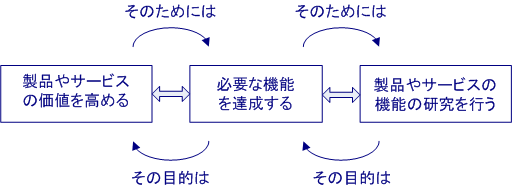
と、つながります。上位の目的と目的との関係は、目的と機能の関係と同じように、相対的な上下関係です。上位が目的で下位が機能です。なぜなら、目的を果たすために機能が必要だからです。
このように、VEの目的と機能を追求し、その上位下位の相対関係を明確にすると、VEがどういうものかが良く分かります。ちなみに、目的と機能の関係について詳しくは、「4-7 目的と機能と手段の関係」で説明いたします。
このようにして、VEそのものにVEを適用し、VEにおけるいろいろな考え方や技術、あるいは進め方について目的と機能を追求してみました。すると、驚くことに、VEが常識では理解できない、「おかしなもの」であることがいろいろ分かってきたのです。これらについては順次説明したします。
また、VVEではこのように、条件、目的、機能などを明確に区別します。基本的な用語は頻繁に使用されるので明確にしておく必要があります。これらが曖昧だと理解が難しくなってしまうからです。
ちなみに、『VE用語の手引き』に書かれている使用者は、製品やサービスの使用者ですから消費者のことです。マーケティング用語としては、あるいは通常は、消費者が用いられます。
VVEでは、マーケティング用語として通常使われている「消費者」や「顧客」という用語を用います。ちなみに、顧客には消費者の他に、購入決定者、及び購入者がおります。例えば、子供が使用する商品を母親が購入を決め、父親が代金を払って購入する場合は、子供が消費者(使用者)、母親が購入決定者、父親が購入者になります。
また、生産者(メーカー)にとっては卸売業者や小売業者も製品の購入者であり顧客になります。したがって、「消費者(使用者)」よりも「顧客」の方が広い概念になります。VEの定義では消費者(使用者)だけを顧客としていますが、VVEでは消費者(使用者)だけでなく、購入決定者や購入者を含めて顧客としています。
ところで、VE技術も発展し、その活用対象も製品やサービスの価値の向上だけでなく、業務価値の向上にも活用されております。そこで、日本バリュー・エンジニアリング協会ではサービスを拡大解釈して業務をサービスに含めております。しかし、組織価値の向上、企業価値の向上などにも活用されているので、やはり定義を改定すべきだと思います。
VEでは基本的な用語の意味が明確になっておりません。このことがVEを分かりにくくしている原因の1つです。今回は、この点について説明いたします。
日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE基本テキスト』には、「機能は、そのものが持っている目的や働きである」と書かれています。つまり、機能は目的や働きである、と書かれているのです。また、同じ日本バリュー・エンジニアリング協会発行の『VE用語の手引』には、「機能の達成度や条件を含めて機能としている」と書かれています。よって、VEでは機能の達成度や条件も機能なのです。
これでは、目的、機能、機能の達成度、条件などの用語の意味の違いが分かりません。『VE基本テキスト』及び『VE用語の手引き』に書かれているこれらの用語の意味からすると、機能は目的であり、機能の達成度であり、条件である、となるので、結局、
機能=目的=機能の達成度=条件
となってしまいます。これでは、何が何だか分かりません。
ちなみに、VVEでは、目的、機能、条件などはそれぞれ別の意味を持った用語で、いずれも広辞苑などの国語辞典で定義されている通りです。
すなわち、広辞苑によれば、目的とは、「成し遂げようと目指す事柄。行為の目指すところ。意図している事柄」です。要約すると、目的とは、「目指すこと、意図していること」です。
また、広辞苑によれば、機能とは、「物の働き。相互に関連し合って全体を構成している各因子が有する固有な役割。また、その役割を果たすこと。作用」です。要約すると、機能とは、「働きや役割」のことです。
また、広辞苑によれば、条件とは、「ある物事の成立または生起のもととなる事柄のうち、それの直接の原因ではないが、それを制約するもの」です。要約すると、条件とは、「物事を制約するもの」です。
ちなみに、VEではなぜこのように、使われる用語の意味が曖昧なのかといいますと、そもそも、VA(価値分析)をVE(価値工学)としたアメリカ国防総省がその原因だと思われます。アメリカ国防総省が発行した『新版・価値分析ハンドブック』には、「VEで機能とは、何者かが意図している特定の目的または用途であると定義している」と書かれています。つまり、「機能=目的または用途である」と定義しているのです。ところが、なぜこのような定義になっているのかは不明です。
なぜなら、VA(VE)の創始者であるローレンス・D・マイルズ氏が書いた『価値分析の進め方』にも『VA/VEシステムと技法』にも、このような機能の定義は書かれていないからです。
Ⓒ 開発&コンサルティング