
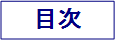
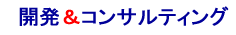
前回説明しましたように、現在では消費者ニーズの多様化による多品種少量生産の増加、消費者ニーズの高度化による製品の高付加価値化、あるいは生産の機械化・IT化などにより、製造原価に占める製造間接費の割合が非常に多くなっています。つまり、元々関連しない製造間接費と操業度とがますます関連しなくなっているのです。
ところが、「製造間接費を操業度に関連する物量基準で配賦する」という『原価計算基準』に基づく方法を現在でも多くの企業が採用しています。このため、正しい原価が計算できません。時代に合わなくなった『原価計算基準』に基づく原価計算では、正しい経営判断ができません。これは重大な問題です。
こうした中で、活動基準原価計算(ABC:Activity Based Costing)は、製造間接費を比較的合理的に各製品やサービスに配賦できると考えられている原価計算方法です。活動基準原価計算は何年ごろ、誰によって、どこの国で開発されたのか、未だに定説がないそうです。しかし、1880年代後半におけるアメリカの製造業で生成し、活用され、開花したそうです。また、Activity Based Costing という名前をつけたのは、R.クーパーとR.カプランだそうです。( 『ABCマネジメント』吉川武男、ジョン・イネス、フォークナー・ミッチェル共著 中央経済社)
さて、活動基準原価計算(ABC)というのは、製造間接費を文字どおり活動(アクティビティ)を基準に配賦しようとするものです。つまり、操業度ではなく、各製品やサービスに関連する活動を基準に配賦しようとするものです。この活動の意味ですが、要するに仕事のことで、作業や業務のことです。よって、活動基準原価計算というのは、製造間接費を各製品やサービスに関連する仕事量(作業量や業務量)を基準にして配賦しようとするものです。
その理由は管理間接部門の仕事量が増大しているからです。つまり、製造間接費のうち主に間接労務費が増大しているからです。また、間接労務費の増大に伴って間接経費も増大しているからです。ちなみに、配賦基準には仕事の時間だけではなく、仕事の時間に比例する仕事の回数や件数などの頻度を用いることもできます。
例えば、運搬作業や修理作業の場合、これらにかかった費用は、運搬時間や修理時間だけでなく、運搬回数や修理回数を配賦基準にすることもできます。また、工場管理部門の業務についても同様に、各製品にかかわった業務時間あるいは業務回数を配賦基準にして配賦することができます。
例えば、設計業務の場合、製品別の設計時間だけでなく、設計回数や設計枚数を配賦基準にします。資材調達や生産管理などの業務についても同様に、各製品にかかわった時間や回数、件数などを配賦基準にします。また、これら製品別にかかわった業務時間を記録しておけば、直接費として各製品に直課することもできます。
以上のように、製造間接費を作業別、業務別の時間や頻度を配賦基準にして、かかわった各製品に直課、又は配賦するのです。つまり、製造間接費を部門別に集計したり、補助部門費を製造部門に配賦したりしないのです。
ということは、製造間接費だけでなく、販売費・一般管理費についても同様に、かかわった製品別に直課、又は配賦できるということです。これが活動基準原価計算の優れた点です。
以上のことから分かるように、活動基準原価計算の基本的考え方は、
ということになります。ですから、製造間接費や販売費・一般管理費を比較的合理的に製品別やサービス別に配賦することができるのです。
活動基準原価計算の基本的な考え方は、「企業で発生するすべてのコストは、製品やサービスの販売によって得られる収益によって回収しなければならない。したがって、すべてのコストは製品やサービスに割り当てる必要がある」と言うものです。よって、製造間接費はもちろん、販売費・一般管理費も各製品やサービスに割り当てるのです。
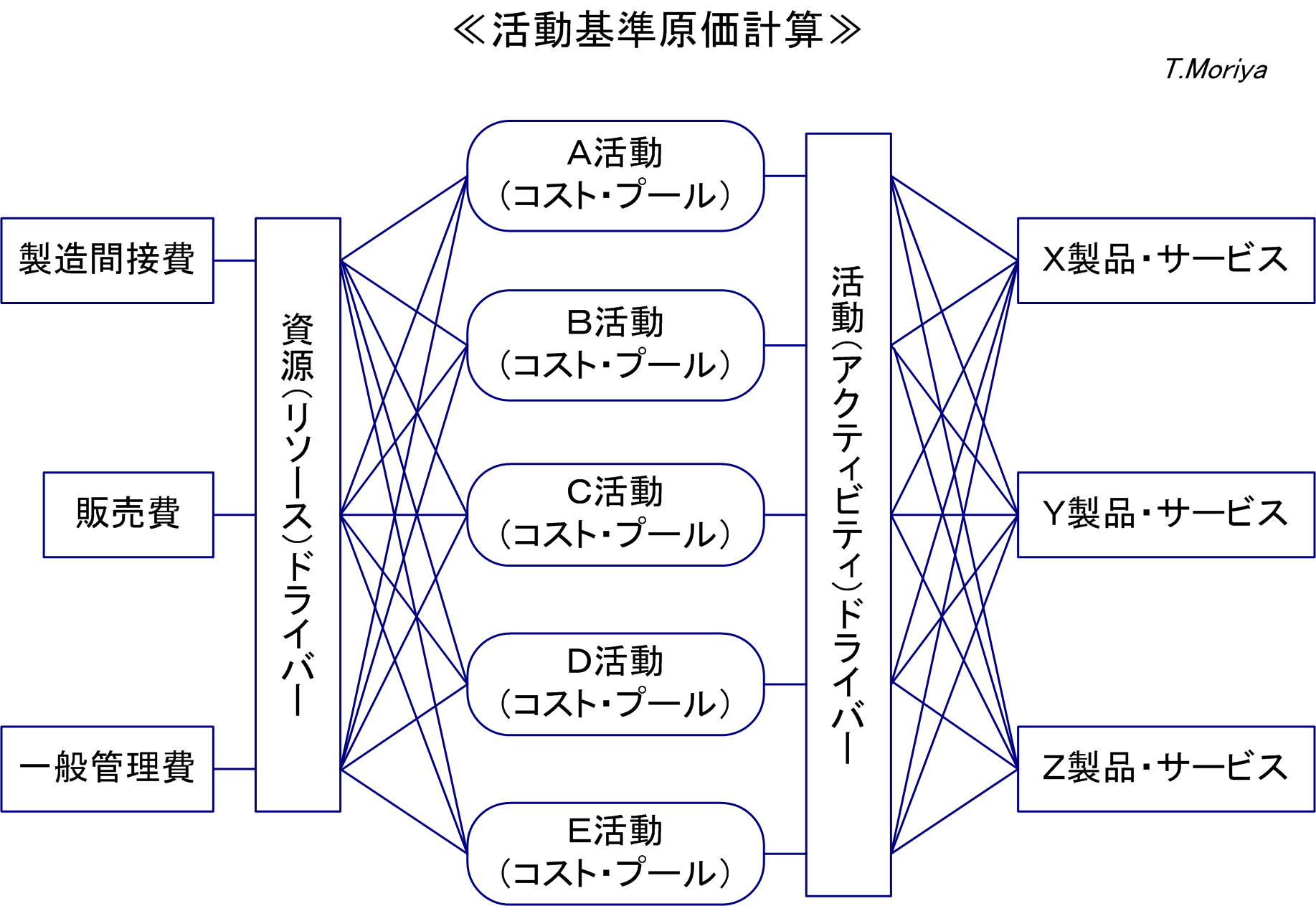
活動基準原価計算の基本的な方法は、「経済的資源を消費する活動ごとにコストを分類・集計し、その活動の利用度合いに応じて製品やサービスにコストを割り当てる」というものです。
ここで、活動基準原価計算に用いられる用語を説明すると、活動ごとにコストを分類・集計したものをコスト・プールと呼びます。また、配賦基準をコスト・ドライバー(コスト決定要因、コスト変動要因)と呼びます。コスト・ドライバーには経済的資源を消費する活動ごとに、コストを配賦する基準となる資源(リソース)ドライバーと、活動の利用度合いによって、製品やサービスにコストを配賦する基準となる活動(アクティビティ)ドライバーとがあります。したがって、活動基準原価計算を行うには活動の分類の仕方とドライバー(配賦基準)を明確にすることが重要になります。
活動基準原価計算を行うには、まず、経済的資源(人、物、設備、資金などの経営資源)を消費する活動ごとにコストをプールする必要があります。このためには、資源を消費する活動ごとにコストを配賦・集計しなければなりません。このための配賦基準が資源(リソース)ドライバーです。資源ドライバーは資源に応じて最適なものを選択します。
また、活動の利用度合いによってコストを製品やサービスに配賦する活動(アクティビティ)ドライバーには、活動時間を配賦基準にした時間ドライバー、活動の回数や件数、人数などの取引頻度を配賦基準にした取引ドライバーがあります。
ちなみに、コスト・ドライバーという言葉は従来から原価管理に使われている言葉ですので、活動基準原価計算においてはコスト・ドライバーという言葉を使わずに、資源(リソース)ドライバーと活動(アクティビティ)ドライバーを使う企業もあります。
例えば、設計変更は従来どおりコスト・ドライバーと呼び、設計に消費される人件費や電気代を設計業務に配賦するのは資源(リソース)ドライバー、製品ごとの設計時間は活動(アクティビティ)ドライバーと呼ぶわけです。つまり、原価管理に用いる用語と活動基準原価計算に用いる用語とを区別するのです。筆者もそのようにした方が間違いがないと思います。
しかし、活動ドライバーをコスト・ドライバーと書いてある活動基準原価計算(ABC)の専門書もあります。したがって、活動ドライバーとコスト・ドライバーを区別していない企業もあります。なお、コスト・ドライバーは、「コストをドライブ(駆動)するもの」の意味ですが、日本語としてはコスト駆動因と呼ぶよりも、コスト決定要因、あるいはコスト変動要因などと呼ぶ方が分かりやすいと思います。
活動基準原価計算のメリットは、製造間接費を製品やサービスごとに比較的正確に割り当てられるだけでなく、販売費、一般管理費なども製品やサービスごとに比較的正確に割り当てられる点です。これによって、製造業だけでなく、建設業、卸・小売業、サービス業、金融業などあらゆる業種で、製品・商品別、サービス別、顧客別、取引先別などの原価が明確になります。
さらに、経営戦略やマーケティング戦略に基づく活動ごとの原価計算を行えば、戦略別の原価と製品やサービスの売上との関係も明確になりますので、戦略実施の費用対効果の測定が可能になるわけです。
活動基準原価計算によって、比較的正確な原価計算が出来るようになると、当然ながら原価管理がいっそう重要になります。従来はいくら原価管理が重要だと言っても、その基となる原価が正しいとは言えないので、原価管理がきちんと出来ませんでした。活動基準原価計算を用いれば、原価管理だけでなく、利益管理、予算管理などもしっかりと出来るようになるわけです。よって、会社は確実に儲かるようになるのです。このため、欧米の企業では活動基準原価計算を導入することが常識になっているようです。
ところが、日本の企業においては、活動基準原価計算(ABC)を導入するのは容易ではありません。日本特有の問題がいろいろあるからです。その第1の問題は日本のホワイトカラーは「活動基準原価計算はめんどうくさい!」と考えるからです。日本の多くの企業では、今までホワイトカラーの業務の原価管理を行ったことがないですから、当然、そのように考えるのです。しかし、欧米ではそのように考える人はいません。
なぜなら、欧米ではホワイトカラー1人ひとりが職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)に基づいて仕事を行っているからです。職務記述書には、職務ごとの時間や頻度が書かれているのです。これによって、業務の原価管理ができるわけです。このために、欧米では活動基準原価計算(ABC)が急速に普及しました。
ところが、活動基準原価計算(ABC)にはもっと根本的な問題もあるのです。そこで次回、それらの問題点について説明し、また、次々回、それらに対する対策について説明したいと思います。
Ⓒ 開発&コンサルティング