
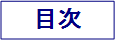
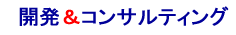
今回から第3章になります。第3章はいろいろなコスト削減・原価低減技術を紹介いたします。今回は、IEによるコスト削減について説明します。
IE(Industrial Engineering)は日本語では、「生産工学」「管理工学」「工業経営学」「経営工学」など、これまでいろいろな呼び方をされて来ましたが、実務ではIEと呼ぶことが多いです。
IEの定義として最もよく知られているのは、アメリカIE協会の定義です。それは、「IEは工学のうちで、人、材料、設備の総合されたシステムを設計し、改善し、設定することを対象とするものである。そのシステムから生ずる結果を明示し、予測し、評価するために、工学的な分析や設計の原理と技法ならびに数学、自然科学、社会科学などの専門的知識と経験などを用いる」というものです。
この定義を見ると、正直に言って筆者には何を意味しているのか良く分かりません。そこで、IEの源流をたどると、1903年にアメリカのF.W.テイラーによって書かれた『工場管理法』が源流であると思われます。その後、『科学的管理法の原理』として新版が発行されました。これらに書かれている、時間研究(時間測定)と動作研究(動作分析)がIEの源流と考えられます。
時間研究(時間測定)はF.W.テイラーが開発し、動作研究(動作分析)はF.W.テイラーの弟子であったギルブレス夫妻が開発したものです。これらは作業研究(ワークスタディー)と呼ばれ、今日に至るまで世界中の工場で活用されています。つまり、IEは科学的管理法が根底にあるのです。
IEが発達するに従い、いろいろな技術が開発され活用されております。よって、人によりいろいろな考え方があります。「科学的に管理する」という考え方からすれば、VE(価値工学)、QC(品質管理)、OR(オペレーションズ・リサーチ)などもIEであり、これらを応用的IEと呼び、テイラーとその弟子が開発した技術を伝統的IEと呼んで区別している人もいます。
その後もいろいろな技術が開発され、どこまでをIEと呼ぶかで、いろいろな考え方があるようですが、いまだに定説がないようです。ちなみに、筆者は伝統的なIEだけをIEと呼び、IEを含めてその後に開発された、VE、QC、OR、TQC、PERT/CPM、ロジスティックス、シックスシグマ、金融工学など、「経営課題解決のための工学的アプローチ」すべてを経営工学と呼んでいます。つまり、F.W.テイラーの著書である『工場管理法』及び『科学的管理法の原理』に書かれている内容と、それを改良した技術だけをIEと呼んでいます。
また、筆者はIEを日本語に訳す場合には、素直に、「管理工学」とするのが良いと思います。なぜなら、F.W.テイラーの『工場管理法』及び『科学的管理法の原理』並びにアメリカIE協会の定義から、IEは管理法であり、工学だからです。
さて、IE(管理工学)は主に工場の現場作業を中心に作業改善を行い、コストを削減したり、納期を短縮したりするために活用されております。また、これらの改善を行ってから作業標準を設定します。作業標準とは作業のあるべき姿であり、標準作業方法、及び標準作業時間(ST:スタンダード・タイム)であり、標準原価計算の基となる原価標準(製品1個あたりの原価)を設定するために使われるものです。
また、作業標準は標準原価計算だけでなく、賃金、生産計画、要員計画などを決めるためにも使われます。したがって、IEなくして工場管理はできないのです。IEは約100年の間、世界中の工場現場で使われています。
IEによるコスト削減は、あるべきコスト(標準原価)の追求と現状コスト(実際原価)の分析に基づき行うもので、両方を兼ね備えた技術ということになります。また、IEは、あるべき姿を描き、現状を分析して問題点を発見し、改善するという分かり易いアプローチであり、また、分析技術もいろいろあって非常に優れた改善技術です。
したがって、日本においても、トヨタ自動車を始め、多くのメーカーで活用しております。トヨタ自動車では新入社員にはIEを徹底的に仕込んでいるということです。なお、トヨタ生産方式を生み出した大野耐一氏はかつて日本IE協会の会長でしたが、「IEはモノづくりの基礎工事みたいなものである」としばしば語っていたということです。
さて、IEの目的は付加価値を高くすることです。IEにおけるあるべき姿は、付加価値を生む工程(作業)を最も良い方法(ワン・ベスト・ウエイ)で実施することです。最も良い方法とは世界中で最も安全に、安く、正しく、速く、楽にできる方法(安、安、正、速、楽)のことです。
その一方で、付加価値を生まない工程(作業)はすべてムダと判断してできるだけ廃止・削減するのです。このためにいろいろな改善技術があります。したがって、ほとんどの作業はこの考え方と技術で改善できるわけですから、工場現場以外にも活用できるわけです。つまり、IEは、ほとんどの作業の改善に活用できるのです。
既に説明してありますが、念のため、付加価値について簡単に復習しておきます。付加価値は売上から外部支払い費用を引いたものです。つまり、会社の純粋な稼ぎです。この稼ぎは会社の経営資本と従業員の労働によって獲得したものです。中小企業の場合、ここでいう従業員には社長も役員も含まれます。よって、社長や役員を含めた全員で稼いだものが付加価値です。ちなみに、大企業の場合は社長や役員は従業員には含まれません。
この稼ぎ(付加価値)を会社と従業員とで山分けするわけです。従業員に対する分け前の比率を労働分配率と言います。従業員に対する分け前は給料やボーナス、あるいは福利厚生費などになります。したがって、稼ぎ(付加価値)が少なければ給料やボーナスは少なくなります。
一方、会社に対する分け前は、主に資本を出してくれた株主に対する配当と会社の社内留保になります。また、税金も払わなければなりません。社内留保は今後の設備投資や運転資金、あるいは不測の事態に備えるための準備金や積立金になります。不測の事態への備えは、例えば、業績が悪化しても給料は払わなければならないので、そのための準備金とか、機械設備が故障したり、老朽化したりした時の買い替えのための積立金などです。
以上の説明でお分かりのように、会社の稼ぎ(付加価値)を増やすことは会社にとって最も重要です。これがIEの目的ですから、どのような会社でもIEの考え方や進め方で改善を進める必要があるのです。とりわけ、従業員にとっては会社の稼ぎ(付加価値)から分け前を多くもらいたいですから、労働分配率を高めたいと思うのが当然です。そのためには、その基となる稼ぎ(付加価値)を多くしなければなりません。
従業員一人当たりの付加価値を労働生産性と呼びます。この労働生産性を高めること、つまり、できるだけ少ない人数で、できるだけ多くの付加価値を獲得することが重要なのです。そして、このための手法がIEなのです。したがって、IEはどのような企業にとっても重要なものです。ですから、IEを知らない経営者、管理者は失格です。
しかし、残念ながら工場現場以外ではあまり活用されておりません。つまり、製造業以外ではあまり活用されておりませんので、他の業種で活用すればかなりの効果が期待できます。実際に筆者がコンサルティグした例で言えば、魚介類や肉類の卸売業者やスーパーマーケットのバックヤードの作業です。つまり、魚や肉の解体、パック詰めや運搬、検査などです。これらの作業は工場の加工組立作業と全く同じなのです。また、建設現場の作業にも活用できます。
要するに、物を動かしたり手足を動かしたりする作業を行っている所では工場と同じように改善できるのです。自動車メーカーや家電メーカーでは、戦後アメリカからIEを導入して以来、ずっと今日までIEを活用して日々作業改善を行って来ました。よって、IEを良く知らないとか、実施したことがないという企業は是非実施して下さい。大きな成果が得られます。
また、現場の直接作業以外でも活用できる分野があります。それが管理間接部門の業務、すなわちデスクワークです。現状の業務実態を把握するためにはIEは欠かせません。例えば、ワークフロー分析はIEの工程分析をデスクワークに適用したものです。昔は事務工程分析と呼ばれていました。しかし、単にワークフロー(仕事の流れ)だけを細かく把握して見える化しても何も改善はできません。作業や業務の付加価値を分析しなければ意味がないのです。IEの目的は付加価値を高めることだからです。
ちなみに、筆者が調べたところ、現在販売されているワークフローと呼ばれるソフトはほとんどが付加価値分析を行っていません。単に、IT(情報)化するために仕事の流れを見える化しているのです。よって、付加価値を生まないムダな仕事をIT化しているのです。これではも何もなりませんし、このためにわざわざ金をかけるわけですから、二重のムダです。
ところで、以前にブームになりました、「ホワイトカラーの知的生産性向上システム」も、実はIEをデスクワークに適用したものです。多くの企業でこのシステムを利用しましたが、残念ながらあまり成果は上がらなかったようです。その理由は明白です。実は、IEには根本的な欠点があるのです。それは、IEによって分析・改善できるのは、物の動きや手足を動かす作業に限られるのです。思考や判断を必要とする知的労働は分析・改善できません。
つまり、目に見える物や手足の動きは分析できますが、目に見えない頭の中までは分析できないのです。したがって、そのような作業や業務に対しては、IEでは改善できませんし、作業標準を設定することもできません。あくまで、IEは目に見える物や手足の動きについて現状実態を分析し、改善するための技術なのです。デスクワークを分析対象にする場合にはこの点を充分に注意する必要があります。
例えば、上司から出張報告書の提出を指示された場合、Aさんは30分で報告書を作成提出し、Bさんは3時間かけて作成提出し、Cさんは3日もかかってようやく作成提出した、などということはよくあることです。そして、それぞれの報告書の内容や作成方法をいくら分析しても、どれが最も良いかは分かりません。 なぜなら、報告書の提出を指示した上司の考え(頭の中)と、それをA、B、C、の3人がどう受け止めているか(頭の中)によって異なるからです。つまり、上司とA、B、C、の3人それぞれに考えを聞かないとどれが良いかは分からないのです。
それなのに、このような思考・判断を伴う業務に対しても、IE技術であるワークフロー分析を行って改善しようとする人たちがいるのです。そのうえ、ITを活用して業務を改善(効率化)するために、DFD(データ・フロー・ダイヤグラム)、ER(エンティティ・リレイション)図、UML(オブジェクト指向に基づく構造化技法)などを使用して分析しようとする人たちがいるのです。
これらは単に、業務をIT化するための分析であって、改善するための分析ではありません。IT化しさえすれば改善できると思い込んでいるのです。IT化しても処理時間が速くなるだけのことで、ムダな業務を削減することはできません。ムダな業務に金をかけて迅速に処理しても何もなりません。二重のムダです。
最近では業務効率化と言えば、ITを活用することが当たり前であるかのように考えられています。しかも、このために、ワークフロー分析を行って現状分析することが盛んに行われています。しかし、業務の価値分析を行わなければ業務の効率化は出来ません。なぜなら、業務に価値があるかないかが分からないからです。
また、業務のあるべき姿が分からないのに問題が分かるわけがありません。問題=あるべき姿-現状、だからです。思考・判断を伴う作業や業務に対してIEを適用しても、その作業や業務が本来どうあるべきか、は分かりません。このような作業や業務の改善・改革・開発にはIEではなく、VEが必要なのです。これについては次回説明いたします。
さて、話を本論に戻します。IEは目に見える物の動きや手足の動き、いわゆる手作業にしか適用できないのです。しかし、逆に言えば、手作業ならばどのような業種の手作業でも適用できるのです。IEには作業の方法研究と時間測定(時間研究)の2つの分野があり、作業方法を改善し、作業の標準時間(ST)を設定するためにいろいろな技術があります。
具体的なIE技術については、第6章で説明いたしますが、IEにはいろいろな技術があり、問題に応じて技術を選択し、適用します。企業にはいろいろな問題が存在し、また、それらがいろいろな原因で発生するからです。IEを適用するポイントは、大まかな分析から次第に細かな分析へと進めることです。なぜなら、大きな問題を解決してから小さな問題を解決する方が効果的だからです。また、問題発生の現象面から分析し、次第にその原因へとさかのぼっていくことです。言ってみれば、宝探しですから、楽しみながら改善することです。
作業者同士で互いに作業方法を改善し、互いに作業時間の測定をして改善効果を確かめ、作業標準を設定するなど職場の人たちでわいわいやると楽しくできると思います。小集団活動でも作業改善がよくテーマになります。
最近は動画が容易に利用できるので、物の動きや手足の動きを動画に記録し、それを仲間同士で見ながら改善を進めるようになりました。仲間の上手な方法を学ぶだけでなく、あるべき姿(最も良い方法)を描くことや改善の方法を学びながら行ってください。そうしないと、時間をかけてもあまり効果的な改善ができません。
ちなみに、動画を利用する方法はいろいろなスポーツや趣味の訓練などにも活用されています。動画を見ながらコーチに悪い所を指摘してもらったり、同じ訓練を受けている人たちが、お互いに仲間の動きを観察して良い所や悪い所を見つけて改善し合ったりする方法です。ですから、難しいことではありません。
実は、この動画を使って改善する方法は昔から行われているIE技術の1つです。昔は主に8mmフィルムを使っていました。動画を使うのは作業を改善するためだけでなく、作業の標準速度を決めるためでもあります。標準作業速度を決めるのは重要なIE技術の1つだからです。なお、現在では多くの工場で作業標準(作業マニュアル)に動画が使われております。また、卸・小売業、あるいはサービス業などでも使われるようになりました。レジ打ち作業、接客作業などの作業標準を動画で作り、その映像を見ながら作業を行えば分かりやすいので早く習得できるからです。