
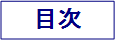
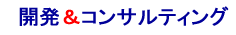
実は、『原価計算基準』及び簿記の教科書に書かれている個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算などの従来の原価計算では正しい原価が計算できないのです。その理由は、製造間接費の配賦が適切ではないからです。と言うのも、通常は製造間接費の配賦基準として操業度に関連するものを用いますが、製造間接費と操業度とは必ずしも関連しないからです。
ご存じのように、製造間接費の配賦基準には、
などがあります。これら以外にもいろいろと考えられるので、配賦に適した基準を用いれば良いのですが、配賦に適した基準があるとは限らないのです。このことは、従来の原価計算における根本的な問題なのです。
『原価計算基準』には、「操業度は、原則として直接作業時間、機械運転時間、生産数量等間接費の発生と関連ある適当な物量基準によって、これを表示する」と書かれています。このように、操業度は間接費の発生と関連ある物量基準で表示することになっているので、間接費の配賦基準に操業度を用いているのです。しかし、そもそも操業度は間接費の発生と関連あるのでしょうか。また、操業度を配賦基準にするのが正しいのでしょうか。そうとは限りません。そこで、この点について検討してみたいと思います。
まず、製造間接費のうち間接労務費の配賦について検討します。例えば、現場監督、運搬工、修理工などの間接作業員の労務費は操業度とは関連しません。
なぜなら、現場監督の仕事は生産が計画通りに行われている時にはあまり忙しくなく、計画通りに行われていない時に忙しくなるからです。つまり、トラブルが多く発生すれば忙しくなるのです。
資材運搬の作業は製品の切り替え時に多くなり、また、使用する材料や部品点数が多い製品の場合に多くなります。点検・修理の作業は機械化・IT化の進展により機械設備が増加したり、機械設備が老朽化したりすると多くなります。
工場管理者(工場管理部門)の間接労務費については、通常、管理対象となる作業員数、又は直接労務費を配賦基準にします。確かに、工場の人事、総務など人に関わる業務は作業員数や直接労務費に関連すると考えられます。
しかし、設計、資材調達、生産計画などの生産準備のための業務や生産管理(品質管理、納期管理、原価管理)、技術管理などの生産実施に関わる管理業務は操業度とは関係ありません。これらの業務は複雑で技術的に難しい製品ほど多くの時間・コストを必要とします。よって、製品の複雑性や技術的難易度などに比例します。
次に、部門別原価の配賦について検討してみます。各部門で発生する費用を部門費として一旦集計し(第1次集計)、部門費のうち補助部門費を各製造部門に配賦し(第2次集計)、そのうえで、各製造部門から各製品に配賦するという方法です。補助部門で発生する費用を各製造部門に配賦する際には、その用役(サービス)の内容と消費量に応じた配賦基準で配賦すれば良いわけです。
さらに、製造間接費を変動費と固定費とに分解して別々に配賦するという方法もあります。つまり、変動費は用役消費量に応じて各製造部門に配賦し、固定費は用役消費能力に応じて各製造部門に配賦するという方法です。ちなみに、通常、製造間接費の予算は公式法変動予算によって変動費と固定費とに分解して編成します。
以上のようにすれば、正確に配賦することができるはずですが、本当にそうでしょうか。製造間接費をそれぞれの補助部門に適した配賦基準で各製造部門に正しく配賦できたとしても、また、製造間接費を変動費と固定費とに分解してそれぞれに適した配賦基準で各製造部門に正しく配賦できたとしても、各製造部門から各製品に配賦する際には、やはり、操業度を基準に配賦するのです。
そもそも、操業度に関連しない費用を、操業度を基準に配賦しても正しい製品別原価は計算できません。しかも、各補助部門費を計算したうえで、各補助部門費⇒各製造部門費⇒各製品、と何度も配賦して、むりやり操業度に関連する費用に変えているように筆者には思えます。まるで不正資金を、銀行を転々と変えることによって正当な資金のようにしてしまう、つまり、洗濯(ロンダリング)してしまうマネー・ロンダリングのようです。
元来、部門費計算を行う目的は、製造に直接かかわらない補助部門の費用(製造間接費)を製品の製造原価に加算し、製品原価を正しく計算するためです。しかし、実務上はむしろ、各部門の原価管理を行い原価責任を明確にするためなのです。その理由として、各部門費の集計を行った後に、部門間相互に発生する用役(サービス)にかかわる費用については相互配賦を行うからです。しかも、より正確に配賦するために何度も相互配賦を行います。補助部門の費用を製造原価に加算するためだけであれば、相互配賦はそれほど必要ないはずです。
たとえ、製造部門別の原価が正しく計算できたとしても、製品別原価が正しく計算できなければ何もなりません。例えば、ある製品の原価率が悪くなった場合に、製造間接費の配賦が正しくなければその原因は分かりません。原因が分からなければ対策の打ちようがないのです。また、原因が分からないのですから、原価高となった部門があったとしても、その部門に責任があるわけではありません。
この製造間接費の配賦については以前から問題とされてきました。しかし、高度経済成長時代は少品種多量生産が主流であり、製造原価に占める製造間接費の割合が少なかったために、それほど大きな問題にはなりませんでした。むしろ当時は、製造直接費に対する製造間接費の割合を直間比率と呼び、製造間接費を削減することに努めていました。
ちなみに、筆者も顧客企業の製造間接費を削減するために業務効率化のコンサルティングを行っていました。しかし、現在に至って、この問題が深刻になってきました。と言うのも、現在では、製造原価に占める製造間接費の割合が急激に増大しているからです。
理由その1は、消費者ニーズの多様化によって、多品種少量生産が当たり前になっているためです。多品種ですから、資材運搬の作業や、工場管理部門の業務に多くの時間・コストがかかります。しかも、少量生産ですから生産量は少ないのです。
仮に、少品種多量生産の製品類と多品種少量生産の製品類とが混在している工場で、これらに共通する製造間接費を直接作業時間、機械運転時間、生産量などの操業度を基準に配賦すると、多品種少量生産の製品類は製造間接費が多くかかっているにもかかわらず少なく配賦されて原価が安くなってしまいます。この問題は多品種少量生産が進展すればするほど深刻になります。
理由その2は、消費者ニーズの高度化によって、製品の高付加価値化が進展しているためです。このために、製品の構造が複雑となり技術的な難易度が高くなって、工場管理部門の費用(製造間接費)が増大しているのですが、このことは操業度とは何の関係もありません。
例えば、A製品とB製品とを製造している企業があるとします。A製品は構造が複雑で技術的に難しく、付加価値が高いとします。このため、設計、資材調達、生産計画、生産管理、技術管理などの業務に時間・コストがかかります。しかし、生産量は少ないとします。一方、B製品は標準品で技術的には容易であり、付加価値が低いとします。しかし、生産量は多いとします。
A製品とB製品とに共通する製造間接費を、直接作業時間や機械運転時間、あるいは生産量などの操業度を基準に配賦すると、当然、A製品の原価は安く、B製品の原価は高くなります。つまり、付加価値の高い製品の原価は安く、付加価値の低い製品の原価が高くなってしまうのです。このようなことは実際に多くの企業で見られます。
理由その3は、現在では機械化・IT化が進み、人による生産が機械設備による生産に移行しているためです。このため、機械設備の減価償却費やプログラム設計費、機械設備やコンピューターの管理費などの製造間接費が増大し、その一方で生産時間は非常に短くなっています。
ちなみに、FA(Factory Automation)やCIM(Computer Integrated Manufacturing)など、高度に発達した工場では製造原価に占める製造間接費の割合が90%以上になっています。CDやDVDの製造がその典型的な例です。これほどではないにしても、機械化・IT化が進んでいる工場では製造間接費の割合が60%以上になっているのです。そのうえ、生産時間(機械運転時間)が非常に短くなっているのです。したがって、機械運転時間を配賦基準にしても正しい製品別原価は計算できません。
以上の理由により、実際には儲かっている製品であるにもかかわらず、儲かっていないように計算されてしまい、その製品の生産を中止してしまった会社があります。また、逆に、実際には儲かっていない製品であるにもかかわらず、儲かっているように計算されてしまい、しかもこの製品が会社の主力製品であったために、いつの間にか業績が悪化し、倒産してしまった会社もあるのです。
現在、多くの企業で採用している旧大蔵省企業会計審議会による『原価計算基準』に基づく原価計算では、正しい原価が計算できないのです。製品別原価が正しく計算できなければ、製品価格を決めることもできないし、いくら儲かるか、あるいはいくら損するかも分からないということです。製品原価が正しくないということは、小売業で考えてみれば、商品の仕入れ値がいくらか分からないということと同じです。
以上の理由により、現在では、『原価計算基準』に従わない企業も増えています。例えば、専用機械や金型などの減価償却費は、『原価計算基準』では間接経費となっていますが、実際には直接経費なので製品に直課する。運搬工や修理工などの間接作業員の労務費(補助部門費)は、製造部門への配賦を行わないで、運搬時間や修理時間、あるいは運搬回数や修理回数を配賦基準にして、製品に直課、又は配賦する。
また、工場管理部門の費用(補助部門費)も製造部門への配賦を行わないで、かかった業務時間や業務回数を基準に製品に配賦する。要するに、製造間接費を製造部門には配賦しないで、製品に直課あるいは配賦するのです。
つまり、各部門の原価や責任を明確にすることと、製品別原価を正しく計算することを切り離すのです。この方が間違いのない原価計算ができるだけでなく、原価高の原因追究がしやすいからです。
さらに、極端な例ですが、生産現場の間接作業の費用は各製品に配賦するが、工場管理部門の費用は各製品に配賦しない、という企業もあります。つまり、工場管理部門の費用は製造原価には含めないで、販売費・一般管理費と同様に期間原価として取り扱う、ということです。
このように、先進的な企業では、独自に原価計算基準を設定して原価計算を行っています。要するに、旧大蔵省企業会計審議会による『原価計算基準』に従う財務会計目的の原価計算と、企業独自の原価計算基準による管理会計目的の原価計算とを区別しているのです。
なお、現在のところ、製造間接費を各製品に比較的正しく配賦できる方法として、活動基準原価計算(ABC)があります。しかし、活動基準原価計算にも問題があります。これについては、次回以降説明いたします。
Ⓒ 開発&コンサルティング