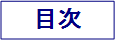
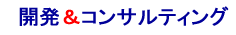
これまで何度も、「経費精算」がムダな業務であることを書きましたが、多くの企業では未だにこのムダな業務を行っているので、改めて実際の事例を書くことにします。
なぜなら、「経費精算」を行っている企業は多くの損失をしているだけでなく、従業員を信用していない証拠でもあるからです。なぜなら、従業員が作成した「経費精算書」をチェックするのが経費精算業務だからです。よって、もし、読者が勤務する会社が未だに「経費精算」を行っていれば、「我が社は従業員を信用していない会社だ」と思って下さい。また、この業務を行っている企業は、その他のチェック業務も非常に多く、確実に衰退する企業なので、転職をお勧めします。
さて、ある一部上場企業が、ムダな業務の典型である「経費清算」をわざわざ時間と金をかけてシステム化し、それによって業務効率化ができたことを自慢げに話すのを聞きました。
まず、このチェック業務にかかっている業務コストを計算すると、1件当たり平均で3,400円になっていることを突き止めたそうです。さすがに一部上場企業です。ほとんどの企業は、この業務コストを計算することさえできないでしょう。なぜなら、ほとんどの企業では業務別時間を測定し、業務別コストを算出していないからです。
そして、この業務をシステム化し運用することによって、1件当たり1,600円にまでコスト削減できたそうです。システム構築のために投資した金額は約1千万円だそうです。
業務コストが1件当たり3,400円マイナス1,600円ですから1,800円のコスト削減になった。全社で経費清算業務が年間1万件ぐらいだから、1,800万円のコスト削減になり、投資金額1千万円を差し引くと800万円のプラスになったと言っています。よって、運用1年で投資の元を取ったと自慢していました。
一方で、経費精算書の計算ミス、金額の書き間違え、あるいは不正による損失などは1件当たり数百円であり、年間1万件とすると数百万円であるということです。私は「馬鹿じゃないの」と言いたくなりました。
年間数百万円の損失を防ぐために、1千万円を投資し、経費清算の業務コストを年間1,600万円かけ、そのうえシステムの運用コストもかけています。どうしてこんな馬鹿なことを行うのでしょうか? それは従業員のミス防止、不正防止のためです。従業員の小さなミスや不正をどうしても許せないのです。いわゆる尻の穴が小さい経営者なのです。
40年以上前、筆者がコンサルタントに成り立てのころ、ある一部上場企業が出張旅費清算の業務を廃止しました。つまり、清算をしないで、あらかじめ決めた金額を支給することにしたのです。その理由は、ミスや不正による損失コストより防止コストの方がはるかに高いことが分かったからです。
では、実際に、この企業ではどのようにして出張旅費の支払いを行っているのでしょうか。まず交通費についてですが、例えば、新幹線を使う場合、普通乗車料金の他に役員にはグリーン席料金を支給し、役員以外には指定席料金を支給します。
ローカル線やバス料金は別途決めた交通費手当を支給します。プリペイドカードを支給する場合もあります。タクシーを使った場合には領収書と引き換えに現金で支払います。宿泊費については役員は1泊2万円、部課長は1泊1万5千円、一般従業員には1泊1万円を支給します。
不足する場合やタクシーの領収書をもらうのを忘れた場合には交通費手当や出張手当の中から各自で負担するのです。つまり、交通費にしろ、宿泊費にしろ予め支給する金額は決まっているので、清算はしないのです。
問題は過不足分です。チェック業務である出張旅費清算を廃止したことにより、どういう問題が生じるかです。当然、ミスや不正が発生することが予想されます。しかし、その心配はありません。まず、交通費ですが、新幹線を使わずに飛行機で行っても自分の車で行っても清算はしません。
よって、自分の車で行って旅費を浮かし飲み代に当てる者がいます。しかし、それでもかまいません。本人の勝手です。ローカル線やバスを使う場合、支給される交通費手当では不足する場合もありますし、逆に多い場合もありますが清算はしません。
また、プリペイドカードを支給する場合、休日に私用で使おうとする者がいます。しかし、休日には使えないように金曜日の退社時には必ず会社に寄ってプリペイドカードを会社に置いて帰宅することを義務付けます。
また、例えば、地方の工場や営業所に勤務している社員が東京に出張し、東京で仕事が終了した後に、プリペイドカードを使って箱根や伊豆の温泉に行って宿泊し翌朝出勤する人がいます。さらに、東京に勤務している営業員が昼間から堂々と日帰りで箱根や伊豆の温泉に行く人もいます。それでも一向にかまいません。仕事さえきちんと行えば問題にはしません。元々営業員は裁量労働制をとっているからです。
出張による宿泊費については、一般従業員の場合には1泊1万円が支給されていますが、仮に8千円のホテルに泊まっても清算しないので2千円は自分のものになります。逆に、1万2千円のホテルに泊まった場合は2千円は自腹ということになります。
このように過不足分を自己負担にした場合、別の問題が生じます。それは税金です。この企業では、最初、所轄する税務署に相談に行きました。そうすると、不足分については不問であるが、過分に支払った分については給料とみなして所得税を取ると言われたらしいです。税務署らしい実に勝手な言い分です。そこで、こちらも反論したそうです。
「過分に支払ったかどうか、また、いくら過分だったかは本人にしか分からない。仮に出張旅費清算をきちんと行ったとしても、実際にいくら使ったかは本人にしか分からない。なぜなら、電車やバスは領収書を発行しないから。よって、税金を計算することはできない」と。
そのうえ、「会社としてはムダな業務を削減し、業務コストを削減して少しでも利益を増やし、その結果、税金を少しでも多く支払うようにした。それなのに、過分に支払った分を従業員の所得とみなして課税するとは、できるもんならやってみろ!」と税務署に言ってやったそうです。
「そもそも、企業会計原則の中に重要性の原則というものがある。企業会計は定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。」
「よって、重要性の乏しいものについては本来の厳密な会計処理によらないで、他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。」「そこで、企業会計原則に基づき、重要性の乏しいものを簡便な方法で処理したのであるから、問題なかろう。」
と反論したそうです。この反論によって税務署も黙ってしまったということです。
さて、昨今、コンプライアンス(法令順守)として内部統制を強化する動きがあります。内部統制に関する日本版SOX法が施行されているにもかかわらず、いつになっても企業の不正がなくならないからです。この法律は、本来は経営者の不正防止が目的です。しかし、このために従業員の不正防止のためのチェックが厳しくなっているのです。
このために、従業員が労働意欲をなくし、業績が悪化しているのです。従業員満足を図り、その結果として顧客満足をもたらせば、業績が向上するのです。このことを忘れ、従業員の些細なミスや不正を許さず、チェック業務を強化するようなことは決して行うべきではありません。
筆者は40年以上前から一部上場企業を始め、多くの企業で業務効率化や業務改革のコンサルティングを行っておりますが、筆者がコンサルティングした会社ではどの会社も出張旅費清算は行っていません。また、従業員が使ったその他の経費の精算も行っていません。
経費の計算自体は経費を使った従業員が行い、経費精算書(経費清算申告書)を作成しますが、会社の業務としてチェックは行わないのです。よって、従業員が申告した通りの金額を支払うわけです。これだけで、会社が従業員を信用していることが分かるので、従業員が満足し、業績が向上するのです。